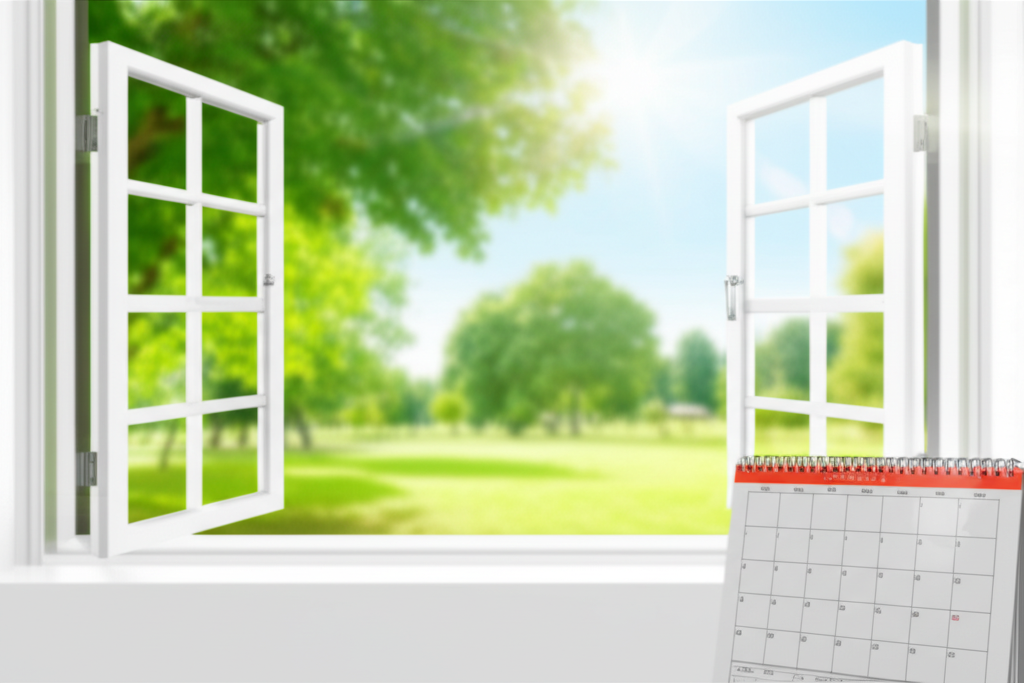自己都合で退職された方にとって、失業保険の受給開始日は気になるポイントです。
原則として2ヶ月の給付制限があるため、再就職活動への備えを万全にするには、正確な情報が欠かせません。
受給開始日を特定する方法を詳しく解説します。
自己都合退職の場合、失業保険は「一体いつから受給できるのだろうか」と疑問に思う方は多いはずです。
2ヶ月の待機期間があることは知っていても、「起算日はいつなのか」「本当に2ヶ月で受給できるのか」といった具体的な疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

自己都合で辞めたら、失業保険はいつもらえるの?

ハローワークで求職の申し込みをしてから、実際に失業保険が振り込まれるまで約2ヶ月半程度の期間が必要です。
この記事でわかること
- 待機期間と給付制限
- 受給開始日の特定方法
- 受給を早めるポイント
- 受給中の注意点
失業保険|自己都合2ヶ月、受給開始日を徹底解説

自己都合で退職した場合、失業保険の受給開始日は原則として2ヶ月後になります。
この期間を正確に理解することで、再就職活動への備えを万全にできます。
自己都合退職の場合の失業保険受給開始日について、具体的な起算日や待機期間を【2ヶ月後、受給開始日を特定する方法】で詳しく解説していきます。
自己都合退職、失業保険受給開始日の疑問
自己都合で退職した場合、「失業保険は一体いつから受給できるのだろうか」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
2ヶ月の待機期間があることは知っていても、「起算日はいつなのか」「本当に2ヶ月で受給できるのか」といった具体的な疑問を抱えている方もいるはずです。
自己都合退職後の失業保険受給に関する疑問を解消するために、【自己都合退職と失業保険受給の関係性】では受給要件や給付制限について詳しく解説します。
自己都合退職と失業保険受給の関係性
自己都合退職でも、雇用保険の加入状況や離職理由によっては失業保険を受給できます。
ただし、会社都合退職とは異なり、給付制限期間が設けられている点が大きな違いです。
自己都合退職と失業保険受給の関係性を理解するために、【2ヶ月の待機期間、起算日を解説】では、給付制限期間や待機期間の起算日について詳しく解説します。
2ヶ月の待機期間、起算日を解説
自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、原則として2ヶ月の給付制限期間があります。
この期間は、ハローワークが失業状態を確認し、再就職活動を促すための期間です。
2ヶ月の待機期間の起算日を正しく理解するために、以下の情報をお伝えします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 待機期間 | ハローワークで求職の申し込みを行った日から7日間 |
| 給付制限期間 | 待機期間満了日の翌日から2ヶ月間 |
2ヶ月後、受給開始日を特定する方法
2ヶ月の給付制限期間が終了したからといって、すぐに失業保険が振り込まれるわけではありません。
実際に受給を開始するためには、ハローワークでの失業認定を受ける必要があります。
失業保険の受給開始日を特定するために、以下のステップを確認しましょう。
- 失業認定:指定された日にハローワークに出向き、失業状態であることと、求職活動を行っていることを申告します。
- 受給開始:失業認定後、通常1週間程度で指定した口座に失業保険が振り込まれます。

失業保険はいつもらえる?

自己都合退職の場合、ハローワークで求職の申し込みをしてから実際に失業保険が振り込まれるまで、約2ヶ月半程度の期間が必要となることを覚えておきましょう。
受給を早めるための2つのポイント
自己都合退職の場合、給付制限期間を短縮することはできませんが、早期の再就職を支援するための制度も存在します。
これらの制度を活用することで、失業期間中の経済的な不安を軽減し、再就職への意欲を高めることができます。
受給開始を早めるために、以下の2つのポイントを意識しましょう。
- 教育訓練給付制度の活用:厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講することで、給付制限期間中でも失業保険を受給できる場合があります。
- 求職活動の積極的な実施:ハローワークの職業相談、求人への応募、面接など、積極的に求職活動を行い、再就職への意欲を示すことが大切です。
失業保険受給、自己都合退職者の疑問を解消
自己都合退職でも失業保険は受給できますが、2ヶ月の給付制限がある点が重要です。
この給付制限期間、受給額、注意点について理解を深めることで、再就職に向けた準備をスムーズに進められます。
各見出しでは、自己都合退職者が失業保険を受給する上で重要なポイントを解説します。
自己都合でも受給可能?
自己都合退職であっても、雇用保険の加入期間などの条件を満たせば失業保険の受給は可能です。
しかし、会社都合退職とは異なり、給付制限という制度があるため、受給開始までに時間がかかることを理解しておきましょう。

自己都合で辞めたら、やっぱり失業保険はもらえないの?

自己都合でも受給できますが、給付制限期間があることを覚えておきましょう。
雇用保険の加入条件は以下の通りです。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 加入期間 | 離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上必要 |
| 働く意思と能力 | 働く意思と能力があること |
| 求職活動 | ハローワークで求職の申し込みを行うこと |
| 離職理由 | 原則として、自己都合退職も対象 |
これらの条件を満たしていれば、自己都合退職でも失業保険の受給資格が得られます。
2ヶ月の給付制限とは?
2ヶ月の給付制限とは、自己都合退職の場合に、失業保険の給付が開始されるまでの待機期間のことです。
この期間中は、失業保険は支給されません。

2ヶ月もお金がないのは困るなぁ…

残念ながら、自己都合退職の場合、給付制限期間を短縮することはできません。
給付制限のルールは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 原則2ヶ月(令和2年10月1日以降の離職に適用) |
| 起算日 | 7日間の待機期間満了日の翌日 |
| 短縮の可能性 | 教育訓練給付制度を活用することで、給付制限期間中でも失業保険を受給できる場合があります。 |
| 過去の自己都合退職回数 | 過去5年間に2回以上自己都合で退職している場合は、給付制限期間が3ヶ月になる場合があります。令和2年10月1日以降に離職した場合、5年間に2回まで給付制限期間が2ヶ月に短縮されています。 |
給付制限期間中は、経済的な準備をしっかりとして、再就職活動に専念できるように計画を立てましょう。
いつから、いくらもらえる?
失業保険は、ハローワークで求職の申し込みをしてから約2ヶ月半後から支給されます。
支給額は、退職前の賃金や年齢などによって異なります。

結局、いつから、いくらもらえるんだろう?

受給開始時期と金額は、個人の状況によって異なるため、ハローワークで確認しましょう。
失業保険の受給開始時期と金額に関する情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給開始時期 | ハローワークで求職の申し込みをしてから約2ヶ月半後 |
| 支給額 | 退職前6ヶ月の給与総額と退職時の年齢で決定 |
| 賃金日額の計算方法 | 賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与合計 ÷ 180 |
| 基本手当日額の計算方法 | 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) |
| 給付日数 | 離職理由、雇用保険加入期間、離職時の年齢で変動。自己都合退職の場合、90~150日 |
正確な受給開始時期や金額を知るためには、ハローワークで詳細な計算をしてもらうことをおすすめします。
知っておくべき注意点
失業保険を受給するにあたって、求職活動を積極的に行うことや、アルバイトの収入を申告することなど、注意すべき点がいくつかあります。
これらの注意点を守らないと、失業保険の受給が停止されたり、不正受給とみなされたりする可能性があります。

受給中に気をつけることはある?

求職活動を積極的に行い、アルバイト収入はきちんと申告しましょう。
注意点に関する情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 求職活動 | 失業認定を受けるためには、原則として、過去4週間に2回以上の求職活動実績が必要です。 |
| アルバイト | 受給中にアルバイトをする場合は、労働時間や収入に制限があります。1日4時間未満、週20時間未満が目安です。 |
| 収入の申告 | アルバイト収入があった場合は、必ずハローワークに申告する必要があります。 |
| 不正受給 | 就職や就労状況を申告しなかったり、求職活動について申告しなかったりすると、不正受給とみなされる可能性があります。 |
失業保険を正しく受給するために、これらの注意点をしっかりと守りましょう。
自己都合退職者向け失業保険申請サポート
初めての申請でも安心
失業保険の申請は複雑で不安に感じるかもしれませんが、正しい知識と準備があれば、スムーズに手続きを進めることが可能です。
初めて申請する方でも安心できるよう、基本的な情報から注意点までを詳しく解説します。
申請時の注意点
申請時には、いくつかの重要な注意点があります。
必要書類の準備、申請期限の確認、そして正確な情報提供です。
これらのポイントをしっかり押さえて、スムーズな申請を目指しましょう。
申請に関する疑問や不明点は、ハローワークに遠慮なく問い合わせることが大切です。
よくある質問(FAQ)
- 自己都合退職の場合、失業保険はいつもらえるのですか?
-
自己都合で退職された場合、ハローワークで求職の申し込みをしてから、7日間の待機期間と原則2ヶ月間の給付制限期間が必要です。
そのため、実際に失業保険が振り込まれるまでには、約2ヶ月半程度の期間がかかります。
- 2ヶ月の給付制限期間は、具体的にいつから始まるのでしょうか?
-
2ヶ月の給付制限期間は、ハローワークに求職の申し込みをした日から7日間の待機期間が満了した日の翌日から起算されます。
- 自己都合退職でも失業保険をもらうための条件はありますか?
-
はい、自己都合退職でも失業保険を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること、働く意思と能力があること、ハローワークで求職の申し込みを行うことなどが主な条件です。
- 失業保険の受給額はどのように計算されるのですか?
-
失業保険の受給額は、退職前6ヶ月の給与総額と退職時の年齢によって決定されます。
具体的には、まず賃金日額を算出し、その金額に給付率(50~80%)をかけたものが基本手当日額となります。
- 失業保険を受給中にアルバイトをすることはできますか?
-
失業保険の受給中にアルバイトをすることは可能ですが、労働時間や収入に制限があります。
1日4時間未満、週20時間未満を目安とし、アルバイト収入があった場合は必ずハローワークに申告する必要があります。
- 失業保険を受給するために、ハローワークでどのような手続きが必要ですか?
-
失業保険を受給するためには、まずハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。
必要な書類としては、離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、振込先口座情報などがあります。
求職申し込み後、「雇用保険受給資格者証」が交付され、雇用保険説明会に参加する必要があります。
まとめ
自己都合で退職された方が失業保険をスムーズに受給できるよう、受給開始日は原則として2ヶ月後になる点を解説しました。
- 自己都合退職でも、雇用保険の加入状況や離職理由によっては失業保険を受給できる
- 7日間の待機期間に加え、原則として2ヶ月の給付制限期間がある
- ハローワークでの失業認定を受ける必要がある
- 求職活動を積極的に行うこと
本記事を参考に、ハローワークで求職の申し込み手続きを進めてみましょう。