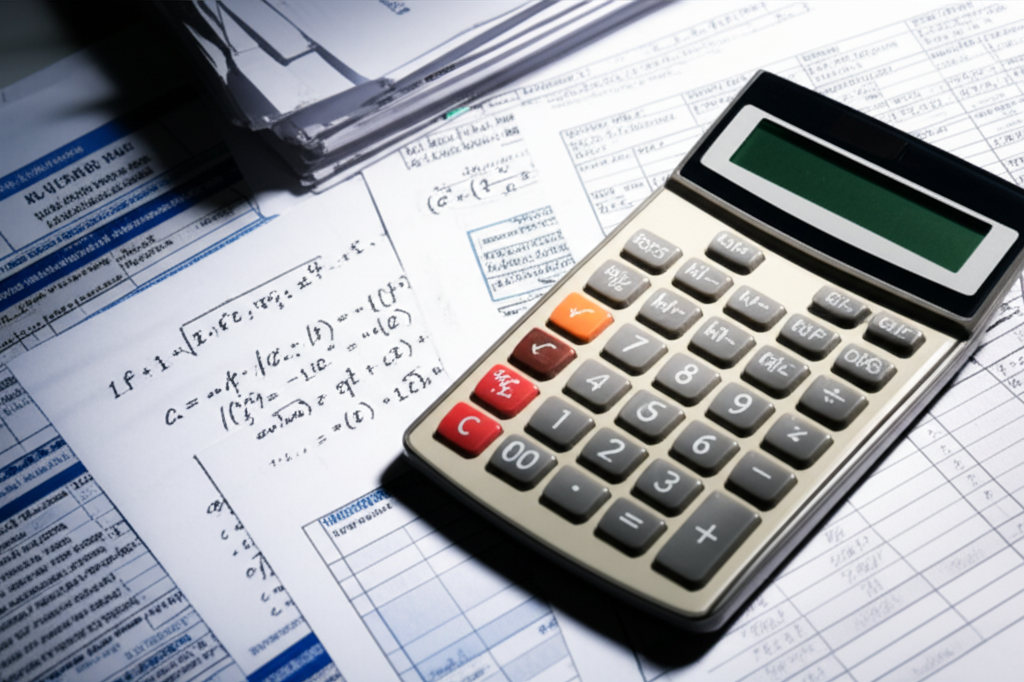退職後の生活を支える失業保険。
受給額は、今後の生活設計を左右するとても大切な要素です。
受給額を事前に把握することで、安心して転職活動に臨めます。
失業保険の計算方法を理解することで、ご自身の受給額を予測できます。
この記事では、計算に必要な情報や、ハローワークでの確認事項をまとめました。
ご自身で受給額を計算し、将来設計に役立てましょう。

失業保険の計算って難しそう…。

3つの要素と計算方法を理解すれば、ご自身でも簡単に計算できます。
この記事でわかること
- 賃金日額の計算方法
- 給付率の確認方法
- 所定給付日数の決定
失業保険の計算方法|受給額算出のポイント

失業保険の受給額を把握することは、今後の生活設計を立てる上で非常に重要です。
失業保険の計算方法を理解することで、受給額を予測し、転職活動中の経済的な不安を軽減できます。
以下に、計算に必要な情報やハローワークでの確認事項をまとめましたので、参考にしてください。
自分で計算する重要性
失業保険の受給額を自分で計算することは、将来設計において不可欠な要素です。
正確な受給額を把握することで、求職活動中の生活費を具体的に計画できます。
また、ハローワークでの手続きをスムーズに進めるための準備にもつながります。

本当に自分で計算する必要があるのかな?

正確な金額を把握し、より現実的な生活設計を立てるために、自分で計算することは有益です。
計算に必要な情報
失業保険の計算には、賃金日額、給付率、所定給付日数の3つの情報が必要です。
これらの情報を基に、基本手当日額と受給総額を算出します。
正確な金額を把握するためには、以下の情報を事前に準備しておくことが重要です。
| 情報 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 賃金日額 | 退職前6ヶ月の給与総額(残業代、通勤手当、住宅手当を含む)を180で割った額 | 賞与、退職金、各種祝い金は含まない/年齢に応じて上限と下限あり |
| 給付率 | 賃金日額に応じて変動する割合(45~80%) | 離職時の年齢によっても異なる |
| 所定給付日数 | 退職理由や雇用保険の加入期間によって異なる日数 | 自己都合退職の場合は90~150日、会社都合退職の場合は90~330日(年齢、雇用保険の被保険者期間で変動) |
ハローワークでの確認事項
ハローワークでは、計算結果の確認や、受給資格に関する相談が可能です。
ハローワークの窓口では、専門の相談員が個別の状況に合わせてアドバイスを提供してくれます。
計算結果に不安がある場合や、受給資格について疑問がある場合は、積極的に相談することをおすすめします。

ハローワークに相談する前に、自分でできることはある?

自分で計算した結果とハローワークの情報を照らし合わせることで、より正確な受給額を把握できます。
受給額を左右する3つの要素
失業保険の受給額は、退職前の賃金と雇用保険の加入期間によって大きく変動します。
受給額を最大化するためには、これらの要素を理解することが大切です。
失業保険の受給額は、賃金日額、給付率、所定給付日数の3つの要素で決定します。
各要素を理解することで、ご自身の受給額をより正確に把握できます。
賃金日額:計算の基礎
賃金日額は、失業保険の基本手当日額を算出するための基礎となる金額です。
賃金日額は、原則として離職日以前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与や退職金は除く)の合計額を180で割って算出します。
例えば、離職前6ヶ月の賃金総額が180万円の場合、賃金日額は1万円です。
ただし、賃金日額には年齢に応じて上限額と下限額が設定されており、上限額を超える場合や下限額に満たない場合は、それぞれ上限額または下限額が適用されます。
2024年8月1日時点での上限額は、29歳以下は13,890円、30歳から44歳は15,430円、45歳から59歳は16,980円、60歳から64歳は16,210円です。
下限額は一律2,746円です。

賃金日額ってどうやって計算するんだろう?

賃金日額は、退職前6ヶ月の給与総額を180日で割って計算します。
給付率:年齢と賃金で変動
給付率は、賃金日額に乗じて基本手当日額を算出するための割合です。
給付率は、離職時の年齢や賃金日額によって変動します。
一般的に、賃金日額が低いほど給付率は高くなり、賃金日額が高いほど給付率は低くなります。
給付率は50%から80%の間で変動し、具体的な数値は厚生労働省のWebサイトやハローワークで確認できます。
例えば、30歳以上45歳未満の場合、賃金日額が低いほど80%に近い給付率が適用され、賃金日額が高いほど50%に近い給付率が適用されます。
所定給付日数:退職理由と加入期間
所定給付日数は、失業保険を受給できる日数のことです。
所定給付日数は、離職理由と雇用保険の被保険者期間によって大きく異なります。
自己都合退職の場合、所定給付日数は90日から150日の範囲で、雇用保険の被保険者期間に応じて決定します。
一方、会社都合退職の場合、所定給付日数は90日から330日の範囲で、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて決定します。
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
| 離職時の年齢 | 雇用保険の被保険者期間 |
|---|---|
| 1年未満 | |
| 30歳未満 | 90日 |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 |
| 45歳以上60歳未満 | 180日 |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 |
失業保険の受給額は、賃金日額、給付率、所定給付日数の3つの要素によって決定します。
ご自身の状況に合わせて各要素を確認し、受給額を正確に把握することが重要です。
自分でできる受給額シミュレーション
失業保険の受給額を自分で計算することで、退職後の生活設計を具体的に立てられます。

ハローワークの窓口で確認する前に、まずはご自身で大まかな金額を把握しておきましょう。
以下では、具体的なシミュレーション方法について、わかりやすく解説します。
特に、簡単シミュレーターの活用、具体的な計算例、注意点と確認事項について詳しく見ていきましょう。
簡単シミュレーターの活用
失業保険の受給額を簡単にシミュレーションできるツールが、Web上で提供されています。
これらのシミュレーターは、いくつかの情報を入力するだけで、自動的に受給額を計算してくれるため、複雑な計算式を理解する必要はありません。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 退職時の年齢 | 離職日時点での年齢を入力 |
| 雇用保険の被保険者期間 | 雇用保険に加入していた期間を入力 |
| 離職理由 | 会社都合退職か自己都合退職かを選択 |
| 離職前6ヶ月の給与総額 | 離職する前の6ヶ月間に支払われた給与の総額(基本給、残業代、各種手当などを含む)を入力 |
これらの情報を入力することで、受給資格の有無やおおよその受給額を把握できます。
ただし、シミュレーターの結果はあくまで目安であり、実際の受給額はハローワークでの審査によって確定することに留意しましょう。
具体的な計算例
シミュレーターを使わずに、自分で受給額を計算することも可能です。
計算に必要な情報は、賃金日額、給付率、所定給付日数の3つです。
- 賃金日額の計算: 退職前6ヶ月の給与総額 ÷ 180
- 基本手当日額の計算: 賃金日額 × 給付率(50~80%、年齢により変動)
- 受給総額の計算: 基本手当日額 × 所定給付日数

失業保険の計算って複雑で難しいな…

計算式に当てはめるだけで、意外と簡単に計算できるんです!
例えば、30歳で会社都合により退職、雇用保険の被保険者期間が5年、退職前6ヶ月の給与総額が180万円の場合を考えてみましょう。
まず、賃金日額は180万円 ÷ 180日 = 1万円となります。
次に、給付率を50%と仮定すると、基本手当日額は1万円 × 50% = 5千円です。
会社都合退職の場合、所定給付日数は90日~330日の間で変動しますが、ここでは120日と仮定します。
最後に、受給総額は5千円 × 120日 = 60万円となります。
これらの計算をすることで、おおよその受給額を把握できます。
注意点と確認事項
失業保険の受給額を計算する際には、いくつかの注意点があります。
まず、給付率は年齢や賃金によって変動するため、正確な給付率をハローワークで確認する必要があります。
また、所定給付日数は退職理由や雇用保険の被保険者期間によって異なるため、こちらもハローワークで確認が必要です。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 給付率 | 年齢や賃金によって変動するため、ハローワークで確認が必要です |
| 所定給付日数 | 退職理由や雇用保険の被保険者期間によって異なるため、ハローワークで確認が必要です |
| 離職理由 | 離職理由によって受給資格や給付制限が異なるため、ハローワークで確認が必要です |
| 受給期間 | 受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、受給開始が遅れると受給期間が短くなるため、注意が必要です |
| アルバイト・パート収入 | 失業保険の受給期間中にアルバイトやパートで収入を得ると、受給額が減額されたり、受給が停止されたりする可能性があるため、ハローワークに相談が必要です |
| その他 | ハローワークでは、求職活動の支援や職業訓練の紹介なども行っています。積極的に活用することで、早期の再就職につなげることができます |
さらに、離職理由によって受給資格や給付制限が異なる点にも注意が必要です。
自己都合退職の場合、給付制限期間があるため、受給開始が遅れる可能性があります。
正確な情報を得るためには、ハローワークに相談することを推奨します。
よくある質問(FAQ)
- 失業保険の計算で、賃金日額の上限額と下限額はいくらですか?
-
賃金日額には年齢に応じて上限額と下限額が設定されています。
2024年8月1日時点での上限額は、29歳以下は13,890円、30歳から44歳は15,430円、45歳から59歳は16,980円、60歳から64歳は16,210円です。
下限額は一律2,746円です。
- 失業保険の計算に必要な給付率は、どのように確認すれば良いですか?
-
給付率は離職時の年齢や賃金日額によって異なり、50%から80%の間で変動します。
具体的な数値は厚生労働省のWebサイトやハローワークで確認できます。
- 自己都合退職の場合、失業保険の所定給付日数はどのように決まりますか?
-
自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間に応じて所定給付日数が決まります。
1年未満の場合は90日、1年以上5年未満は90日、5年以上10年未満は120日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
- 会社都合退職の場合、失業保険の所定給付日数はどのように決まりますか?
-
会社都合退職の場合、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって所定給付日数が決まります。
90日から330日の範囲で変動し、詳細はハローワークで確認できます。
- 失業保険の受給額を計算できるWeb上のシミュレーターはありますか?
-
失業保険の受給額を簡単にシミュレーションできるツールがWeb上で提供されています。
退職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由、離職前6ヶ月の給与総額などの情報を入力することで、おおよその受給額を把握できます。
- 失業保険の計算に関して、ハローワークに相談する前に自分でできることはありますか?
-
Web上のシミュレーターを利用したり、ご自身の賃金日額、給付率、所定給付日数を把握して、計算式に当てはめることで、おおよその受給額を計算できます。
まとめ
この記事では、退職後の生活を支える失業保険の計算方法について、重要なポイントをわかりやすく解説しています。
ご自身の受給額を把握することは、今後の生活設計において非常に大切です。
- 失業保険の計算には、賃金日額、給付率、所定給付日数の3つの要素が必要
- Web上のシミュレーターを活用すると、簡単に受給額をシミュレーション可能
- ハローワークでは、計算結果の確認や受給資格に関する相談が可能
- 離職理由や雇用保険の加入期間によって、受給額や受給期間が異なる
この記事を参考に、失業保険の受給額を計算し、ハローワークで詳細を確認して、より安心して転職活動を進めていきましょう。