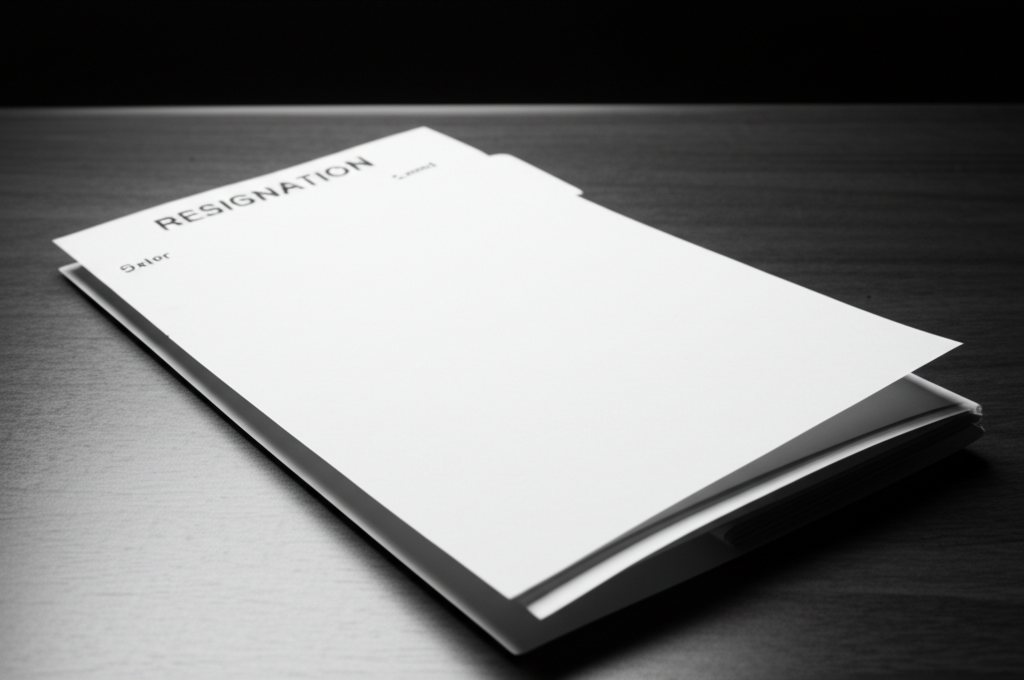退職の意向を伝えるのは、誰にとっても緊張する瞬間です。
会社への伝え方を間違えると、今後の関係に影響が出る可能性も否定できません。
だからこそ、事前の準備と心構えが大切です。
この記事では、退職を円満に、そしてスムーズに進めるための具体的なノウハウを解説します。
退職の意思を伝えるタイミングや、上司への伝え方、退職理由別の例文など、知っておくべき情報を網羅的にご紹介します。

退職の伝え方、難しそう…

例文集を参考に、状況に応じた伝え方を実践することで、円満な退職へとつなげられます。
この記事でわかること
- 退職を伝える際のポイント
- 状況別の例文集
- 退職理由別の伝え方
- 円満退職を実現するための行動指針
退職を円満に伝えるための準備

退職を円満に伝えるためには、事前の準備が非常に重要です。
ここでは、退職の意思を伝える際のポイント、退職希望日の明確化、上司への感謝の伝え方について解説します。
退職の意思を伝える重要ポイント
退職の意思を伝える際には、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、退職の意思は、退職希望日の1〜2ヶ月前までに直属の上司に伝える必要があります。
これは、会社側が後任の選定や業務の引継ぎを行うために必要な期間だからです。
次に、伝えるタイミングも重要です。
繁忙期や人事異動の時期は避け、上司の都合の良い日時を確認し、2人きりで話せる静かな場所を選びましょう。
また、退職の意思を伝える際には、感謝の気持ちを忘れずに伝えることが大切です。
「これまでお世話になったことへの感謝」や「退職後も会社が発展することを願っている」という気持ちを伝えることで、円満な退職につながります。

退職の意思を伝えるのは、なんだか気まずいなぁ…

感謝の気持ちを伝えることで、円満な退職につなげられます。
退職希望日を明確にする必要性
退職希望日を明確にすることは、会社との調整をスムーズに進める上で不可欠です。
退職希望日を伝えることで、会社側は後任の選定や業務の引継ぎの計画を立てやすくなります。
退職希望日は、法律上は退職の意思表示から2週間後とされていますが、実際には業務の引継ぎ期間を考慮して、1〜2ヶ月後とするのが一般的です。
退職希望日を伝える際には、具体的な日付を伝えるようにしましょう。
例えば、「〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談させていただけないでしょうか。
」のように伝えます。
また、退職希望日は、会社の状況や自分の業務の状況を考慮して、上司と相談して決定することが大切です。

退職希望日って、いつにすれば良いんだろう?

退職希望日は、会社の状況や自分の業務の状況を考慮して、上司と相談して決定しましょう。
上司への感謝を伝える心構え
退職を伝える際、上司への感謝を伝えることは、非常に大切です。
上司は、あなたのキャリアにおいて、指導やサポートをしてくれた重要な存在です。
これまでの感謝の気持ちを伝えることで、良好な関係を保ちながら、円満に退職することができます。
感謝の気持ちを伝える際には、具体的なエピソードを交えて伝えるのが効果的です。
例えば、「〇〇のプロジェクトでご指導いただいたおかげで、目標を達成することができました。
」や「〇〇の研修に参加させていただいたことで、スキルアップすることができました。
」のように伝えます。
また、退職後も上司との関係を続けたい場合は、連絡先を交換したり、近況報告をする機会を設けたりするのも良いでしょう。

感謝の気持ちを伝えるって、なんだか照れくさいな…

具体的なエピソードを交えて伝えることで、感謝の気持ちが伝わりやすくなります。
状況別退職の伝え方例文集
退職の意向を伝える際には、状況に応じた適切な例文を使用することが重要です。
スムーズな退職を実現するためには、相手に失礼なく、かつ確実に意図を伝える必要があります。
以下では、直属の上司、人事担当者、同僚、取引先という4つの異なる対象者への伝え方について、具体的な例文を交えて解説します。
この記事の例文を参考に、状況に応じた伝え方を実践することで、円満な退職へとつなげることが可能です。
直属の上司に伝える例文
直属の上司への伝え方は、今後の会社生活にも影響を与える可能性があるため、特に慎重に行う必要があります。
退職の意向を伝える際は、感謝の気持ちを述べるとともに、退職理由を明確に伝えましょう。
以下に、直属の上司に伝える際の例文を示します。
「〇〇部長、いつも大変お世話になっております。
本日は、少しお時間を頂戴できますでしょうか。
実は、以前から検討しておりましたキャリアプランに基づき、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談させていただけないでしょうか。
これまで〇〇部で〇年間、様々業務に携わらせていただき、大変感謝しております。
今回の決断は、長年の夢であった〇〇を実現するためのもので、大変悩んだ末の結論でございます。
後任への引継ぎなど、退職に向けてしっかりと準備を進めて参りますので、ご迷惑をおかけすることのないよう努めてまいります。
まずは、ご相談という形でご連絡させていただきました。
改めて、お時間を頂戴できますでしょうか。」
人事担当者に伝える例文
人事担当者への伝え方は、退職手続きを円滑に進めるために重要です。
退職の意思を明確に伝え、必要な書類や手続きについて確認しましょう。
以下に、人事担当者に伝える際の例文を示します。
「〇〇様、お世話になっております。
〇〇部の〇〇です。
この度、一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご連絡いたしました。
つきましては、退職に関する手続きについてご教示いただけますでしょうか。
必要な書類や手続きの流れ、また、今後のスケジュールについてお伺いしたいと存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご対応いただけますと幸いです。」
同僚に伝える例文
同僚への伝え方は、今後の関係性を考慮し、配慮が必要です。
退職の意向を伝える際は、感謝の気持ちを述べるとともに、退職理由を簡潔に伝えましょう。
以下に、同僚に伝える際の例文を示します。
「〇〇さん、お疲れ様です。
〇〇です。
突然のご報告で恐縮なのですが、〇月〇日をもって退職することになりました。
これまで〇〇さんと一緒に仕事ができて、本当に感謝しています。
〇〇さんのサポートなしでは、今の自分はなかったと思っています。
退職後は、〇〇の分野で新しいことに挑戦したいと考えています。
短い間でしたが、〇〇さんと一緒に働くことができて、本当に楽しかったです。
また、どこかでお会いできることを楽しみにしています。」
取引先に伝える例文
取引先への伝え方は、会社の代表として、今後の関係性を考慮する必要があります。
退職の意向を伝える際は、感謝の気持ちを述べるとともに、後任担当者を紹介しましょう。
以下に、取引先に伝える際の例文を示します。
「〇〇株式会社 〇〇様
いつも大変お世話になっております。
〇〇株式会社の〇〇です。
突然のご連絡で大変恐縮ではございますが、私、〇〇は〇月〇日をもって退職することとなりました。
〇〇様には、〇〇のプロジェクトで大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
後任は、〇〇が担当させていただきます。
〇〇は、〇〇の分野で豊富な知識と経験を持っており、必ず〇〇様のお役に立てると確信しております。
〇〇には、改めてご挨拶にお伺いさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇様には、これまで多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございました。
今後とも、弊社にご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」
退職理由別の例文と伝え方のコツ
退職理由を伝える際には、正直かつポジティブな表現を心がけることが重要です。
円満な退職を実現するために、各理由別の例文と伝え方のコツを参考に、上司や同僚に誠意をもって伝えましょう。
株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査結果も踏まえ、具体的な理由と伝え方について、詳しく解説していきます。
キャリアアップを理由にする例文
キャリアアップを理由とする場合、将来の目標と現在の会社では実現できない点を明確にすることが大切です。
例えば、より専門性の高い分野に挑戦したい、新しいスキルを習得したい、といった具体的な目標を伝えることで、上司も納得しやすくなります。
キャリアアップを理由にする例文と伝え方について解説していきます。
例文
「これまで〇〇の業務に携わってきましたが、今後は××の分野で専門性を高めたいという思いが強くなりました。
つきましては、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご承認いただけますでしょうか。」
家庭の事情を理由にする例文
家庭の事情を理由とする場合、詳細を伝える必要はありませんが、退職せざるを得ない状況であることを丁寧に説明することが重要です。
例えば、親の介護、配偶者の転勤、自身の体調不良などが挙げられます。
家庭の事情を理由にする例文と伝え方について解説していきます。
例文
「一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご承認いただけますでしょうか。
詳細につきましては、お会いした際にご説明させていただきます。」
体調不良を理由にする例文
体調不良を理由とする場合、無理をして働くことが難しい状況であることを具体的に説明することが大切です。
医師の診断書を提示することで、より理解を得やすくなります。
今後のキャリアについて、ポジティブな姿勢を示すことも重要です。
体調不良を理由にする例文と伝え方について解説していきます。
例文
「体調を崩してしまい、医師からも当面の間、療養に専念するよう指示を受けました。
つきましては、大変申し訳ございませんが、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご承認いただけますでしょうか。」
ポジティブな退職理由への言い換え
ネガティブな退職理由を伝える場合、ポジティブな表現に言い換えることで、円満な退職に繋げることができます。
例えば、「給与が低い」という理由を「より自身のスキルを活かせる環境で、キャリアアップを目指したい」と言い換えることができます。
株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、退職理由の上位には労働環境や給与、人間関係などが挙げられていますが、これらのネガティブな理由をそのまま伝えるのではなく、ポジティブな表現に言い換えることが重要です。
退職理由を伝える際の注意点
退職理由を伝える際には、会社への不満や批判を避けることが重要です。
また、退職の意思が固いことを明確に伝えることも大切です。
退職理由を伝える際の注意点を守り、円満な退職を目指しましょう。
円満退職を実現するための行動指針
円満退職を実現するためには、計画的な準備と丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
スムーズな退職は、会社への感謝の気持ちを示すとともに、自身のキャリアにとってもプラスとなります。
以下に、円満退職を実現するための具体的な行動指針をまとめました。
退職日の調整から、必要な手続き、そして退職理由の伝え方まで、詳細に解説していきます。
退職日の調整と引継ぎの準備
退職日を調整する際には、会社の繁忙期を避けるなど、会社の状況を考慮することが大切です。
具体的には、プロジェクトの区切りや人事異動の時期などを考慮し、上司と相談しながら決定します。
また、後任者への引継ぎをスムーズに行えるよう、業務内容や進捗状況をまとめた引継ぎ資料を作成し、口頭での説明と併せて、確実に業務を引き継げるように準備しましょう。
退職願・退職届の作成と提出
退職願と退職届は、会社の規定に従って正確に作成し、提出する必要があります。
退職願は、退職の意思を伝えるためのもので、退職届は、退職を正式に申請するためのものです。
多くの企業では、退職に関する手続きやフォーマットが定められているため、事前に人事部や上司に確認し、必要な書類を入手しましょう。
提出のタイミングも重要で、一般的には退職希望日の1ヶ月〜2ヶ月前に提出することが望ましいです。
退職後の手続きに関する情報収集
退職後の手続きに関する情報を事前に収集することで、退職後の生活をスムーズにスタートできます。
具体的には、雇用保険、健康保険、年金などの手続きについて、必要な書類や手続き場所、期日などを確認しましょう。
例えば、雇用保険の失業給付を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要になります。
また、健康保険は、国民健康保険に加入するか、会社の任意継続制度を利用するかを選択する必要があります。
株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査から学ぶ退職理由
株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、退職理由の上位には、労働環境や給与、人間関係などが挙げられています。
しかし、これらのネガティブな理由をそのまま伝えるのではなく、ポジティブな表現に言い換えることが円満退職につながります。
例えば、「給与が低い」という理由を「より自身のスキルを活かせる環境で、キャリアアップを目指したい」と言い換えることができます。
また、「人間関係が悪い」という理由を「新しい環境で、自分の能力を最大限に発揮したい」と伝えることも有効です。
よくある質問(FAQ)
- 退職を伝える際、上司が忙しそうな場合はどうすれば良いですか?
-
上司が多忙な場合は、メールで事前にアポイントを取り、時間をもらえないか相談しましょう。
その際、退職に関する重要な話であることを伝え、理解と協力をお願いすることが大切です。
- 退職の意思を伝える際、直接会うのが難しい場合はどうすれば良いですか?
-
やむを得ない事情で直接会うのが難しい場合は、電話で退職の意思を伝えても構いません。
ただし、メールやLINEのみで伝えるのは避けましょう。
電話で伝えた後、改めて正式な書面(退職届)を提出することが重要です。
- 退職理由を伝える際、会社への不満を言っても良いですか?
-
退職理由を伝える際は、会社への不満や批判は避けるのが賢明です。
ネガティブな発言は相手に不快感を与え、円満な退職を妨げる可能性があります。
退職後も業界内で繋がる可能性も考慮し、ポジティブな理由を伝えるように心がけましょう。
- 退職の意思を伝えた後、引き止められた場合はどうすれば良いですか?
-
退職の意思が固い場合は、毅然とした態度で退職の意思を伝えましょう。
ただし、感謝の気持ちを忘れずに、丁寧に説明することが大切です。
将来のキャリアプランや、退職によって実現したいことを具体的に伝えることで、理解を得やすくなります。
- 退職届はいつ、誰に提出すれば良いですか?
-
退職届は、退職希望日の1〜2ヶ月前までに、直属の上司に提出するのが一般的です。
会社の規定によっては異なる場合があるため、事前に人事部や上司に確認しておきましょう。
提出する際には、感謝の気持ちを添えて、丁寧に渡すことが大切です。
- 退職後の手続きで、特に注意すべき点はありますか?
-
退職後の手続きで特に注意すべき点は、雇用保険、健康保険、年金の手続きです。
これらの手続きは、退職後の生活を支える上で非常に重要です。
必要な書類や手続き場所、期日などを事前に確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
まとめ
この記事では、退職を円満に進めるための伝え方を解説しました。
退職の意向は、退職希望日の1〜2ヶ月前までに直属の上司に伝えることが重要です。
- 退職の意思を伝える際のポイント
- 状況別の例文集
- 退職理由別の伝え方のコツ
今回ご紹介した例文やポイントを参考に、あなたの状況に合わせてアレンジし、スムーズな退職を実現しましょう。
「退職したら失業保険もらえるでしょ…」
そう思って辞めた人、けっこう後悔してます。
- ✅ 自己都合でも最短7日で受給スタート
- ✅ 10万円〜170万円以上もらえた事例も
- ✅ 成功率97%以上の専門サポート付き
通院歴やメンタル不調のある方は
むしろ受給率が上がるケースも。
・26歳(勤続 2年)月収25万円 → 約115万円
・23歳(勤続 3年)月収20万円 → 約131万円
・40歳(勤続15年)月収30万円 → 約168万円
・31歳(勤続 6年)月収35万円 → 約184万円
※受給額は申請条件や状況により異なります
「あの時、押せばよかった」
不安がいっぱいで、画面のボタンを眺めるだけだった過去の自分。
あれから数ヶ月、給付金は期限切れで申請できず。
通帳には数万円、心には後悔だけが残っている…。
未来のあなたが、そんな後悔をしないように。
今、この10秒が、分かれ道になるかもしれません。
※退職済みの方も申請できる場合があります