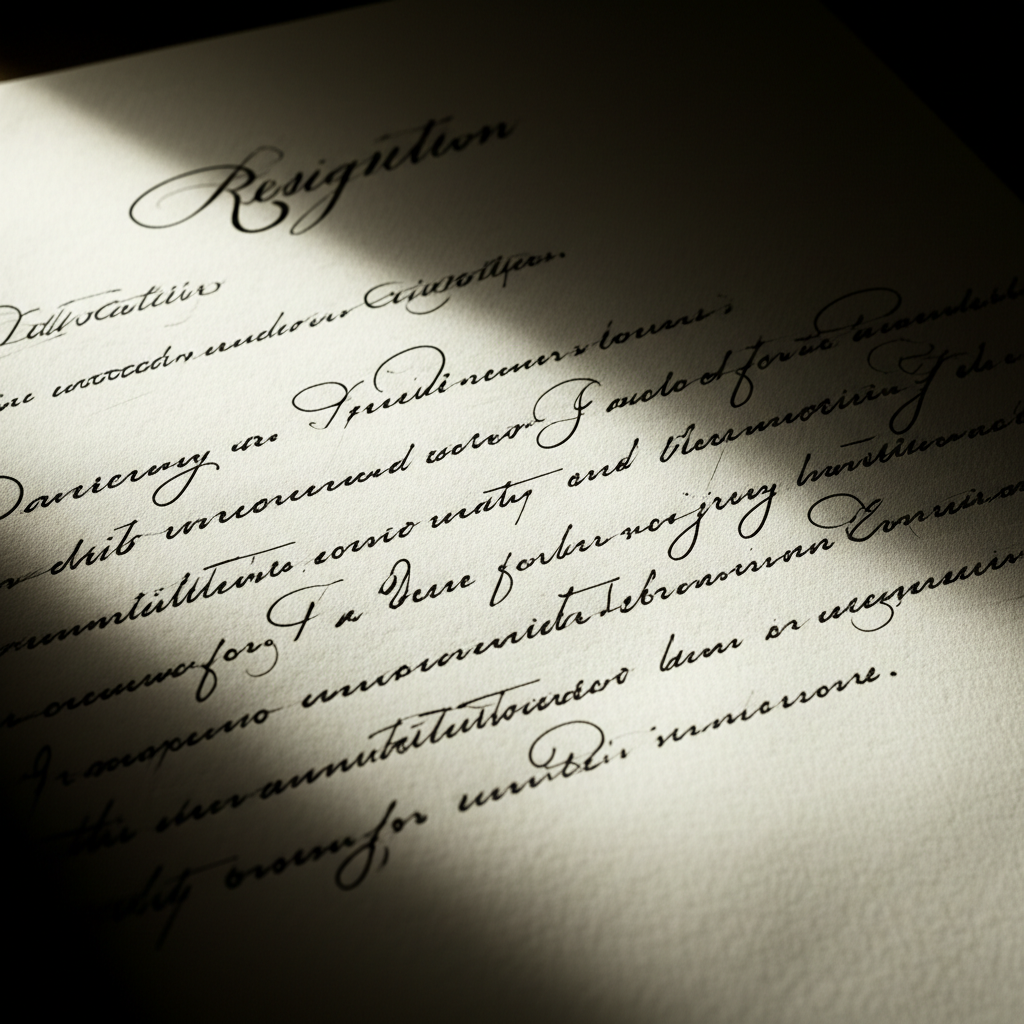退職届を手書きで横書きにする際、何に注意すれば良いか不安ではありませんか? 企業から書式を指定されていない場合、自分で用意する必要があります。
退職届は、退職の意思を企業に伝えるための重要な書類だからこそ、失礼なく、スムーズに手続きを進めたいものです。
この記事では、手書き横書きの退職届の書き方について、用紙や筆記具の選び方から、レイアウト、退職理由の書き方、封筒への入れ方、提出時のマナーまで、詳しく解説します。

手書きで退職届を書いて、企業の担当者に失礼だと思われないかな?

手書きの退職届は、丁寧な印象を与えるので、横書きのマナーを守って作成しましょう。
この記事でわかること
- 手書き横書きの退職届の基本
- 用紙と筆記具の選び方
- 横書きのレイアウト
- 退職理由の書き方
退職届|手書き横書きの基本
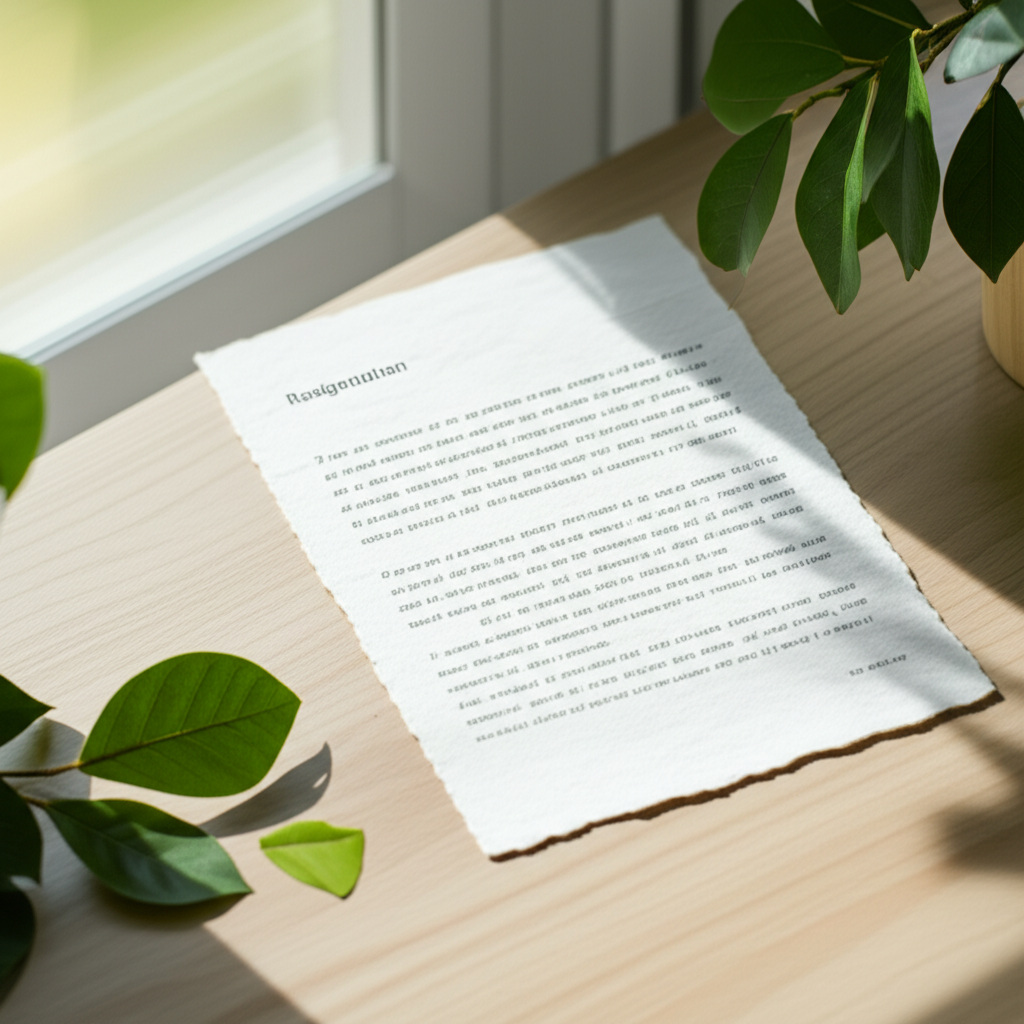
退職届を手書きで横書きする際は、丁寧さと正確さが重要です。
退職届の基本、横書きのメリット、手書きの重要性を理解することで、スムーズな退職へと繋がります。
各項目の詳細は、以下で詳しく解説していきます。
退職届とは
退職届とは、会社や組織に対して、従業員が退職の意思を正式に伝えるための書類です。

退職届って、そもそも何のために書くんだろう?

退職の意思を会社に伝える、大切な書類です。
- 退職の意思を明確に伝える
- 退職日を確定する
- 会社との合意を形成する
- 後々のトラブルを避ける
横書きのメリット
横書きの退職届には、現代的で読みやすいというメリットがあります。
- パソコンで作成しやすい
- 数字や日付が書きやすい
- 文章が短くまとまりやすい
- フォーマルな印象を与えにくい
手書きの重要性
手書きの退職届は、丁寧さや誠意を伝えることができます。
特に、これまでお世話になった会社や上司への感謝の気持ちを伝えたい場合に有効です。

パソコンで作っちゃダメなのかな?

手書きの方が気持ちが伝わりやすいとされています。
- 気持ちが伝わりやすい
- 印象が良くなる可能性がある
- パソコンスキルに左右されない
- 企業の文化によっては手書きが好まれる
手書き横書き退職届の書き方
退職届を手書き横書きで作成する際、重要なのは、丁寧さと正確さです。
各項目の書き方をしっかりと理解し、心を込めて作成することで、円満な退職へと繋がります。
以下に、退職届を手書き横書きで作成する際の各ステップについて詳しく解説しますので、該当箇所を参照ください。
用紙と筆記具の準備
退職届に使用する用紙と筆記具は、社会人としてのマナーを示す大切な要素です。
使用する用紙と筆記具に配慮することで、会社への敬意を表し、スムーズな手続きに繋がりやすくなります。
ここでは、退職届に最適な用紙と筆記具について解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙の種類 | A4またはB5サイズの白い便箋 |
| 紙質 | 上質紙またはコピー用紙 |
| 筆記具 | 黒色のインクのボールペンまたは万年筆 |
| その他 | 修正液や修正テープは使用しない、書き損じに注意 |

退職届ってコピー用紙でも大丈夫ですか?

上質紙を使用すると、より丁寧な印象になります。
横書きのレイアウト
横書きの退職届は、従来の縦書きとは異なるレイアウトで作成する必要があります。
正しいレイアウトで作成することで、読みやすく丁寧な印象を与えることが可能です。
以下に、横書きの退職届の基本的なレイアウトについて説明します。
- 右上に退職日を記載: 「2024年5月31日」のように、退職する年月日を記載
- 宛名を記載: 会社名と代表取締役社長の名前を記載し、敬称として「殿」を付ける
- 例:「株式会社〇〇 代表取締役社長〇〇殿」
- 所属部署と氏名を記載: 自分の所属部署と氏名を、宛名よりも下の位置に記載し、捺印する
- 例:「〇〇部 〇〇」
- 中央に「退職届」と記載: 用紙の中央に「退職届」と記載
- 本文:
- 「私儀」または「私事」で書き始める
- 退職理由は「一身上の都合により」と記載するのが一般的
- 「この度、一身上の都合により、2024年5月31日をもって退職させていただきます。」のように、退職する意思と具体的な退職日を明記
- 右下に「以上」と記載: 本文の最後に「以上」と記載
退職理由の記載例
退職理由の書き方は、退職届の印象を左右する重要な要素です。
退職理由を適切に記載することで、会社との関係を良好に保ち、円満な退職に繋げることができます。
ここでは、退職理由の記載例と注意点について解説します。
| 理由 | 記載例 |
|---|---|
| 自己都合 | 一身上の都合により |
| 会社都合 | 〇〇のため |
| その他の理由 | 病気療養のため、家庭の事情により、キャリアアップのため、スキルアップのため、起業のため |

退職理由って具体的に書いた方が良いですか?

自己都合の場合は、「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。
封筒への入れ方
退職届を封筒に入れる際、折り方や封入方法にもマナーがあります。
正しい方法で封入することで、相手に失礼なく、 formal な印象を与えることができます。
以下に、退職届の封筒への入れ方について解説します。
- 退職届を三つ折りにする
- 白い封筒(長形3号または長形4号)を用意し、表面に「退職届」と記載
- 裏面には、自分の所属部署と氏名を記載
- 退職届を封筒に入れ、封をする
提出時のマナー
退職届を提出する際には、社会人として適切なマナーを守ることが大切です。
相手への配慮を忘れずに、失礼のないように提出することで、良好な関係を維持し、円満な退職に繋がります。
以下に、退職届を提出する際のマナーについて解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出時期 | 会社の就業規則で定められた期日までに提出する |
| 提出方法 | 上司に直接手渡しするのが望ましいが、状況に応じて郵送も可能 |
| その他 | 提出前にコピーを取り、控えとして保管しておきましょう。退職の意思を伝える際には、感謝の気持ちを伝えることが大切です。退職後も良好な関係を築けるように心がけましょう |
退職届提出後の手続き
退職届を提出した後は、会社と従業員の間でさまざまな手続きが必要になります。
退職後の手続きをスムーズに進めるために、必要書類の確認、会社への返却物、受け取る書類、退職後の手続きについて確認しましょう。
必要書類の確認
退職にあたって必要となる書類は、個人の状況や会社の規定によって異なります。
事前に人事担当者や上司に確認し、不足のないように準備を進めましょう。

何から準備すればいいの?

まずは、会社から指示された必要書類を確認しましょう。
| 書類の種類 | 概要 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の加入を証明する書類。失業給付の受給手続きに必要となる。 |
| 年金手帳 | 年金の加入状況を記録した手帳。退職後の国民年金加入手続きに必要となる。 |
| 源泉徴収票 | 1年間の所得と所得税額を証明する書類。確定申告に必要となる。 |
| 離職票 | 雇用保険の失業給付を申請する際に必要な書類。 |
| 住民税に関する手続き書類 | 住民税の納付方法を決定するための書類。 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の資格を喪失したことを証明する書類。国民健康保険への加入手続きに必要となる。 |
| 退職証明書 | 会社を退職したことを証明する書類。転職先への提出や、各種手続きに必要となる場合がある。 |
| 確定拠出年金に関する書類 | 確定拠出年金に加入していた場合、年金資産の移管や脱退一時金の受け取りに必要な書類。 |
会社への返却物
会社から貸与されていたものは、退職日までにすべて返却する必要があります。
返却漏れがないよう、リストを作成して確認しながら準備を進めましょう。

会社に何を返せばいいの?

会社から借りているものは、すべて返却しましょう。
| 返却物 | 概要 |
|---|---|
| 健康保険被保険者証 | 健康保険の資格を喪失するため、会社に返却する。 |
| 社員証 | 会社の社員であることを証明する身分証。 |
| 制服 | 会社から貸与されていた制服。クリーニングに出してから返却するのがマナー。 |
| 事務用品 | 会社から支給されていた文房具や備品。 |
| 会社のパソコン | 業務で使用していたパソコン。 |
| 会社の携帯電話 | 業務で使用していた携帯電話。 |
| 業務関連書類 | 顧客リストや業務マニュアルなど、業務に関する書類。 |
| その他 | 会社から貸与されていた物品(ロッカーの鍵など)。 |
受け取る書類
退職後、様々な手続きで必要となる書類があります。
会社から受け取る書類は、退職後の生活に大きく影響するため、必ず確認しておきましょう。

どんな書類を受け取ればいいの?

退職後の手続きに必要な書類を、確実に受け取りましょう。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の加入を証明する書類。ハローワークで失業給付を申請する際に必要。 |
| 離職票 | 失業給付の手続きに必要な書類。退職理由や賃金などが記載されている。 |
| 源泉徴収票 | 所得税の確定申告に必要な書類。1年間の所得と所得税額が記載されている。 |
| 年金手帳 | 国民年金への加入手続きなどに使用。 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への加入手続きなどに使用。 |
| 退職証明書 | 退職した事実を証明する書類。転職先への提出や、各種手続きで必要となる場合がある。 |
| 確定拠出年金(企業型)の加入者資格喪失のお知らせ | 確定拠出年金(企業型)に加入していた場合、退職後の手続きについて記載された書類。 |
退職後の手続き
退職後は、健康保険や年金、税金など、様々な手続きが必要になります。
手続きを怠ると、将来の年金受給額が減ったり、税金の滞納が発生したりする可能性があります。

退職後って何をする必要があるの?

退職後の手続きをしっかり行い、安心して新しい生活をスタートさせましょう。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 健康保険 | 以下のいずれかの手続きを行う:1. 任意継続被保険者制度に加入する、2. 国民健康保険に加入する、3. 家族の健康保険の被扶養者になる。 |
| 年金 | 以下のいずれかの手続きを行う:1. 国民年金に加入する、2. 厚生年金に加入する(転職した場合)。 |
| 雇用保険 | 失業給付を受給する場合、ハローワークで求職の申し込みと受給の手続きを行う。 |
| 確定申告 | 退職した年の所得について、確定申告を行う(通常は翌年の2月16日から3月15日まで)。 |
| 住民税 | 退職後の住民税の納付方法について、市区町村の窓口で手続きを行う(特別徴収から普通徴収への切り替えなど)。 |
退職後の手続きは多岐にわたりますが、一つひとつ確実に行うことが大切です。
不明な点があれば、会社の担当者や関係機関に問い合わせるようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
- 退職届は手書きで横書きでも良いですか?
-
会社指定の書式がない場合、手書きで横書きの退職届でも問題ありません。
横書きは現代的で読みやすいというメリットがあります。
- 退職届の用紙はコピー用紙でも大丈夫ですか?
-
コピー用紙でも使用できますが、上質紙を使用すると、より丁寧な印象になります。
- 退職理由を具体的に書いた方が良いですか?
-
自己都合の場合は、「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。
- 退職届はいつまでに提出すれば良いですか?
-
会社の就業規則で定められた期日までに提出する必要があります。
一般的には、退職希望日の1〜2ヶ月前までに申し出ることが多いです。
- 退職届を提出する際、上司に手渡しする以外に方法ありますか?
-
上司に直接手渡しするのが望ましいですが、状況に応じて郵送も可能です。
- 退職届を提出した後、何をする必要がありますか?
-
退職届提出後は、会社からの指示に従い、必要書類の確認、会社への返却物の準備、受け取る書類の確認、退職後の手続きなどを行います。
まとめ
この記事では、退職届を手書き横書きで作成する際のマナーや注意点について解説しました。
特に手書きの退職届は丁寧な印象を与えるため、横書きのマナーを守って作成することが重要です。
- 手書き横書きの退職届の基本
- 用紙と筆記具の選び方
- 横書きのレイアウト
この記事を参考に、退職届の作成と提出をスムーズに進め、円満な退職につなげてください。
「退職したら失業保険もらえるでしょ…」
そう思って辞めた人、けっこう後悔してます。
- ✅ 自己都合でも最短7日で受給スタート
- ✅ 10万円〜170万円以上もらえた事例も
- ✅ 成功率97%以上の専門サポート付き
通院歴やメンタル不調のある方は
むしろ受給率が上がるケースも。
・26歳(勤続 2年)月収25万円 → 約115万円
・23歳(勤続 3年)月収20万円 → 約131万円
・40歳(勤続15年)月収30万円 → 約168万円
・31歳(勤続 6年)月収35万円 → 約184万円
※受給額は申請条件や状況により異なります
※退職済みの方も申請できる場合があります