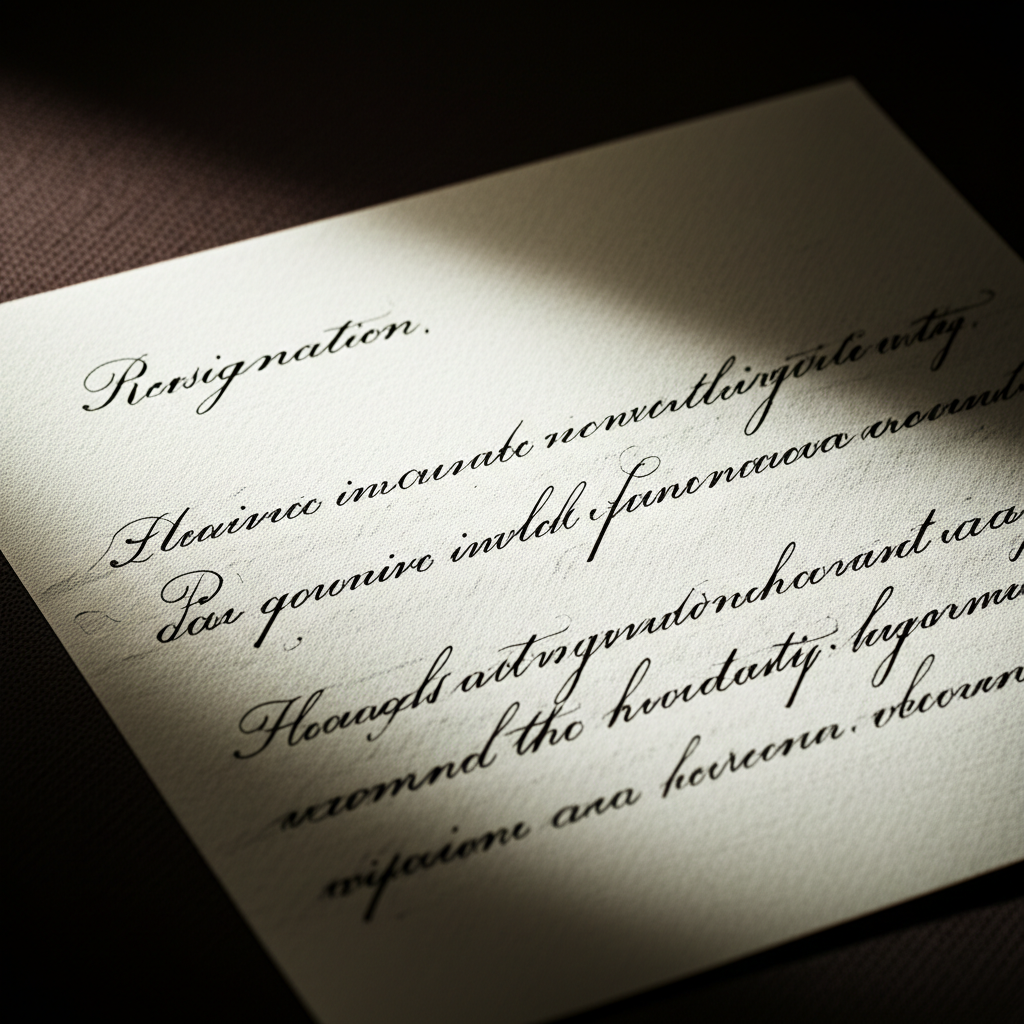退職は、あなたのキャリアにおける重要な転換点です。
会社への感謝の気持ちを込め、円満に退職するためには、退職届の作成が不可欠です。
しかし、手書きの退職届には、書き方や便箋の選び方など、知っておくべきマナーが多く存在します。
退職届を便箋に手書きすることは、PCで作成するよりも丁寧な印象を与え、あなたの真摯な気持ちを伝える有効な手段です。
この記事では、手書きで退職届を作成する際のマナーや注意点、さらに便箋や筆記具の選び方から封筒への入れ方、渡し方まで、あなたの退職を成功に導くための情報を網羅的に解説します。

便箋に手書きで退職届を書く際、どんなことに気をつければいいんだろう?

手書きの退職届は、あなたの誠意と感謝の気持ちを伝える大切な機会です。心を込めて丁寧に作成しましょう。
この記事でわかること
- 退職届の書き方
- 便箋と筆記具の選び方
- 封筒への入れ方と渡し方
退職届の手書き:便箋で好印象を与える書き方

退職届を手書きで便箋に書くことは、丁寧な印象を与え、退職の意思を真摯に伝えるために重要です。
ここでは、退職届を便箋で書く際の重要性と、手書きが与える印象とマナーについて解説します。
これらのポイントを理解することで、会社への感謝の気持ちを示し、円満な退職へとつなげることができるでしょう。
退職という人生の転機を、美しい手書きの退職届で飾りましょう。
退職届を便箋で書く重要性
退職届を便箋で手書きすることは、会社の規定で定められている場合や、特別な事情がない限り、一般的におすすめです。

便箋で書く必要ってあるのかな?

退職届はPCで作成しても問題ありませんが、手書きには気持ちが伝わるという良さがあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 丁寧さ | 手書きはPC作成よりも丁寧な印象を与え、感謝の気持ちを伝えやすい |
| マナー | 会社によっては手書きを指定する場合があるため、事前に確認が必要 |
| 企業の文化 | 伝統を重んじる企業では、手書きの退職届が好まれる傾向がある |
| 個性 | 手書きの文字には個性が表れ、退職という人生の節目に、自分の気持ちを込めることができる |
| 例外 | 会社で退職届のフォーマットが指定されている場合や、PCでの作成が推奨されている場合は、それに従う |
| 心理的影響 | 手書きで書くことで、退職という決断を改めて見つめ直し、気持ちの整理ができる |
| 時間と手間 | 手書きには時間と手間がかかるため、退職の意思が固いことを示すことができる |
| 誤字脱字 | 手書きの場合、誤字脱字に注意する必要がある。修正液の使用は避け、書き損じた場合は新しい便箋に書き直すことがマナー |
| インクの色 | 黒色のインクを使用する。鉛筆や消せるボールペンの使用は避ける |
| ペン | 万年筆や水性ボールペンを使用すると、より丁寧な印象になる |
退職届を手書きで便箋に書くことは、感謝の気持ちや誠意を示すための有効な手段です。
会社の文化や規定を確認した上で、心を込めて作成しましょう。
手書きが与える印象とマナー
手書きの退職届は、相手に誠意と敬意を示すとともに、退職に対する真剣な思いを伝えることができます。

手書きで書く場合、どんなことに注意すればいいの?

退職届を手書きで作成する際は、文字の丁寧さや用紙の選び方など、細かい部分にも気を配りましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 文字の丁寧さ | 楷書で丁寧に書く。誤字脱字がないように注意 |
| 用紙の選び方 | 白無地の便箋を使用する。派手な色や柄物は避ける |
| インクの色 | 黒色のインクを使用する。鉛筆や消せるボールペンは使用しない |
| 修正方法 | 修正液や修正テープは使用しない。間違えた場合は新しい便箋に書き直す |
| 全体的な印象 | 丁寧で誠実な印象を与えるように心がける |
| 退職理由 | 具体的な不満を避け、「一身上の都合」と記載するのが一般的 |
| 封筒の選び方 | 白無地の封筒を使用する。郵便番号欄がないものを選ぶ |
| 封筒への記載 | 表面に「退職届」と記載し、裏面に所属部署名と氏名を記載する |
| 提出方法 | 直接手渡しが原則。やむを得ない場合は郵送する前に上司に相談する |
| 提出時期 | 退職日の1ヶ月前までに提出するのが一般的。会社の就業規則を確認する |
| その他の注意点 | 退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝える。退職届は、上司と合意した上で提出する。退職の撤回は原則として認められないため、慎重に検討する。 |
手書きの退職届は、単なる事務手続きではなく、感謝の気持ちと誠意を伝えるための大切な機会です。
心を込めて丁寧に作成し、円満な退職につなげましょう。
便箋と筆記具の選び方:退職の意思を伝える準備
退職の意思を伝える退職届は、社会人として最後の書類となるため、失礼のないように丁寧に作成することが重要です。
便箋と筆記具を選ぶ際には、相手に与える印象を考慮し、誠意が伝わるように心がけましょう。
ここでは、便箋と筆記具の選び方について解説します。
以下の情報を参考に、退職の準備を進めてください。
便箋サイズの選び方:B5判がおすすめ
便箋のサイズは、B5判(182×257mm)またはA4判(210×297mm)が一般的ですが、B5判がより丁寧な印象を与えます。
理由として、B5判は退職届を三つ折りにして封筒に入れる際に、ちょうど良いサイズであるためです。
A4判を使用する場合は、四つ折りで封入することになります。
便箋の種類:無地が基本
便箋の種類は、白無地を選ぶことが基本です。
理由として、白無地の便箋は、フォーマルな場面で広く使用され、退職届の重要性を伝える上で適切であるためです。
罫線入りの便箋を使用する場合は、薄いグレーやブルーのシンプルな罫線を選び、派手な色や柄物は避けましょう。
ペンの種類:万年筆か水性ボールペン
退職届を作成する際のペンの種類は、万年筆か水性ボールペンが最適です。
理由として、万年筆や水性ボールペンは、インクの色が濃く、文字に深みが出るため、より丁寧な印象を与えることができるためです。
インクの色:黒色を使用
インクの色は、黒色を使用することが基本です。
黒色のインクは、公的な書類やビジネス文書で一般的に使用され、正式な印象を与えます。
青色のインクは、場合によってはカジュアルな印象を与える可能性があるため、避けた方が良いでしょう。
その他の筆記具:鉛筆や修正液はNG
退職届の作成には、鉛筆や消せるボールペン、修正液の使用は厳禁です。
理由として、これらの筆記具は、書き換えや改ざんの可能性があり、正式な書類としての信頼性を損なうためです。
万が一、書き間違えてしまった場合は、新しい便箋に書き直すようにしましょう。
手書き退職届の書き方:作成手順と注意点
退職届を手書きで作成する際は、丁寧さと正確さが非常に重要です。
手書きならではの温かみを伝えることで、円満な退職へと繋げられます。
以下に、作成手順と注意点をまとめました。
各項目の詳細については、Web検索でテンプレートを入手したり、記載項目を丁寧に確認することで、より正確な退職届を作成できます。
退職届のテンプレート:Web 検索で入手
退職届の作成に不安がある場合は、Web上で提供されているテンプレートの利用が有効です。
様々なサイトで無料のテンプレートが提供されており、WordやPDF形式でダウンロードできます。

テンプレートはどこで手に入るの?

Word形式でダウンロードできるサイトや、退職届の書き方見本がセットになった商品もあります。
記載項目1:書き出しは「私儀」
退職届の書き出しには、「私儀(わたくしぎ)」または「私事(わたくしごと)」を使用するのが一般的です。
これは、自身のことを謙譲して述べる際に用いられる言葉で、退職届のようなフォーマルな文書に適しています。

「私儀」ってどういう意味?

「私儀」は、改まった文書で使用される、自分のことをへりくだって表現する言葉です。
記載項目2:退職理由
退職理由の書き方について、自己都合退職の場合は「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。
詳細な理由を記載する必要はありません。
退職理由を具体的に記載したい場合は、会社の規定や就業規則を確認し、適切な表現を用いるようにしましょう。
記載項目3:退職日
退職日は、会社と合意した上で決定した年月日を記載します。
退職日の日付は、上司と相談して決定しましょう。

退職日はいつにすれば良いの?

一般的には、会社の就業規則に則り、1ヶ月前までに申し出るのがマナーです。
記載項目4:届出年月日
届出年月日は、実際に退職届を提出する日付を記載します。
退職日と混同しないように注意が必要です。

いつの日付を書けばいいの?

退職届を会社に提出する日を記載します。
記載項目5:所属部署名・氏名
所属部署名と氏名は、退職届を提出する時点での正式な名称を記載します。
部署名は略さずに正式名称で記入し、氏名は楷書で丁寧に書きましょう。
記載項目6:捺印
捺印は、氏名の右側(横書きの場合は下側)に、認印または実印を押印します。
シャチハタは避けましょう。
捺印が必須かどうかは会社の規定によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
全体を通して:丁寧な字で記入
手書きの退職届は、丁寧に書くことが最も重要です。
読みやすい字で、誤字脱字がないように注意しましょう。
修正液や修正テープの使用は避け、間違えた場合は新しい用紙に書き直すのがマナーです。
退職届の封筒:入れ方と渡し方
退職届を封筒に入れる際、正しいマナーを守ることは非常に重要です。
封筒の選び方から記載方法、退職届の折り方、そして渡し方まで、丁寧に行うことで、円満な退職へと繋がります。
ここでは、各項目について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
封筒の選び方:白無地が最適
退職届を入れる封筒は、白無地の封筒を選ぶのが最も適切です。
郵便番号欄がないものを選ぶと、より丁寧な印象を与えられます。

どんな封筒を選べば良いか迷うなぁ。

白無地の封筒を選べば、間違いありません。
退職届に使用する封筒の種類を下記にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 色 | 白無地 |
| 郵便番号欄 | なし |
| 素材 | 厚めの紙 |
| その他 | 中身が透けないものを選ぶ |
退職届は、会社への感謝の気持ちと、新たなスタートへの決意を示す大切な書類です。
だからこそ、封筒選びにも気を配り、丁寧な印象を与えましょう。
封筒サイズ:長形4号または3号
封筒のサイズは、退職届の用紙サイズに合わせて選びましょう。
B5サイズの用紙には長形4号(90×205mm)、A4サイズの用紙には長形3号(120×235mm)が適切です。

A4の用紙しかないけど、長形4号の封筒じゃダメかな?

長形3号の封筒であれば、A4用紙でも問題ありません。
退職届の用紙サイズと封筒サイズの対応を下記にまとめました。
| 用紙サイズ | 封筒サイズ |
|---|---|
| B5 | 長形4号 |
| A4 | 長形3号 |
適切なサイズの封筒を選ぶことで、退職届が綺麗に収まり、受け取った相手にも好印象を与えられます。
100円ショップやコンビニエンスストアでも購入できるので、手軽に準備できます。
封筒への記載:表面と裏面
封筒の表面には、中央に「退職届」と記載しましょう。
手書きでも印刷でも構いませんが、丁寧に書くことが大切です。
裏面には、左下に所属部署名と氏名を記載します。

封筒の書き方って、何か決まりがあるのかな?

表面と裏面に記載する内容を守れば、問題ありません。
封筒の表面と裏面の記載内容を下記にまとめました。
| 封筒 | 記載内容 |
|---|---|
| 表面 | 中央に「退職届」と記載 |
| 裏面 | 左下に所属部署名と氏名を記載 |
誤字脱字がないか、記載内容に間違いがないか、提出前に必ず確認しましょう。
丁寧に記載することで、退職の意思をしっかりと伝えることができます。
退職届の折り方と入れ方:三つ折りが基本
退職届は、三つ折りにして封筒に入れるのが基本です。
まず、退職届を表面が内側になるように三等分に折ります。
そして、封筒の表から見て、書き出しが右上になるように入れましょう。

退職届って、どうやって折って入れれば良いんだろう?

三つ折りにして、封筒に入れた時に書き出しが右上になるようにしましょう。
退職届の折り方と封筒への入れ方を下記にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 折り方 | 三つ折り |
| 入れ方 | 封筒の表から見て、書き出しが右上になるように入れる |
退職届を折る際には、できるだけ丁寧に、折り目が歪まないように注意しましょう。
綺麗に折って封筒に入れることで、相手に失礼な印象を与えることを避けられます。
渡し方:直接手渡しが原則
退職届は、原則として直属の上司に直接手渡しするのがマナーです。
渡す際には、退職の意思を改めて伝え、お世話になったことへの感謝の気持ちを伝えましょう。
やむを得ない理由で手渡しが難しい場合は、事前に上司に連絡し、郵送しても良いか確認を取りましょう。

退職届って、誰に、どうやって渡せば良いのかな?

直属の上司に、直接手渡しするのが基本です。
退職届の渡し方を下記にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 渡し方 | 直属の上司に手渡し |
| タイミング | 退職日の1ヶ月〜2週間前 |
| その他 | 退職の意思を伝え、感謝の気持ちを伝える |
退職は、会社との関係を円満に終わらせるための重要な機会です。
退職届の提出も、その一環として、丁寧に行うように心がけましょう。
退職後の手続き:円満退職のために
退職は新たなスタートを切るための重要な転換期です。
退職後の手続きをスムーズに進めることで、次のステップに安心して進めます。
退職前に確認すべき事項、退職後の手続き、そして転職活動について解説します。
これらの情報を把握しておくことで、退職後の生活設計をスムーズに進められます。
退職前に確認すべき事項:有給消化や必要書類
退職前に確認すべき事項として、有給休暇の消化と必要書類の確認が挙げられます。
有給休暇は労働者の権利であり、退職日までに計画的に消化することで、心身ともにリフレッシュできます。
必要書類の確認も重要です。
源泉徴収票や雇用保険被保険者証など、退職後の手続きに必要な書類がいくつかあります。
これらの書類は、失業保険の申請や転職先での手続きに必要となるため、必ず確認しておきましょう。

有給休暇って、退職前に全部消化できるのかな?

有給休暇の残日数を確認し、会社の規定に基づいて計画的に取得しましょう。
退職後の手続き:離職票や雇用保険
退職後の手続きとして、離職票の受け取りと雇用保険の申請があります。
離職票は、退職した会社から発行される公的な書類で、雇用保険の申請に必要です。
雇用保険は、失業中の生活を支えるための給付金であり、一定の条件を満たすことで受給できます。
雇用保険の申請は、原則として離職日の翌日から1年以内に行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離職票 | 雇用保険の申請に必要な書類。退職した会社から発行される |
| 雇用保険 | 失業中の生活を支えるための給付金。受給には一定の条件を満たす必要あり |
| 申請期限 | 原則として離職日の翌日から1年以内 |
転職活動:スムーズな移行のために
退職後の転職活動は、計画的に進めることが重要です。
まずは、自己分析を行い、自分のスキルや経験、キャリア目標を明確にしましょう。
求人情報の収集も大切です。
転職サイトや転職エージェントを活用し、自分に合った求人を見つけるために、情報収集を行いましょう。
面接対策も忘れずに行い、自己PRや志望動機を効果的に伝えられるように準備しましょう。
よくある質問(FAQ)
- 退職届を手書きで書く場合、どのようなペンを使えば良いですか?
-
万年筆や水性ボールペンの使用がおすすめです。
これらのペンはインクの色が濃く、文字に深みが出るため、退職届に丁寧な印象を与えることができます。
- 退職届の封筒の表面には何を書けば良いですか?
-
封筒の表面中央には「退職届」と記載します。
手書きでも印刷でも構いませんが、丁寧に書くことが大切です。
- 退職届を提出する際、退職の意思は口頭でも伝えるべきですか?
-
はい、退職の意思はまず直属の上司に口頭で伝えるのがマナーです。
退職届は、上司と合意した上で提出するようにしましょう。
- 退職届の封筒はどこで購入できますか?
-
100円ショップやコンビニエンスストアなどでも購入できます。
白色で郵便番号欄がない封筒を選ぶと、より丁寧な印象になります。
- 退職届を書き間違えた場合、修正液を使っても良いですか?
-
修正液や修正テープの使用は避けて、新しい便箋に書き直すのがマナーです。
書き損じがないよう、丁寧に作成しましょう。
- 退職届を郵送しても良いですか?
-
原則として直属の上司に直接手渡しするのがマナーです。
やむを得ない理由で手渡しが難しい場合は、事前に上司に連絡し、郵送しても良いか確認を取りましょう。
まとめ
この記事では、退職届を手書きで便箋に書く際のマナーと書き方について解説しました。
特に、手書きの退職届は、丁寧な印象を与え、退職の意思を真摯に伝えるために重要です。
- 便箋はB5判の白無地を選ぶ
- 筆記具は万年筆か水性ボールペンを使用し、インクの色は黒色を選ぶ
- 退職理由は「一身上の都合により」と記載するのが一般的
- 封筒は白無地を選び、表面に「退職届」と記載する
この記事を参考に、心を込めて丁寧に退職届を作成し、円満な退職につなげましょう。