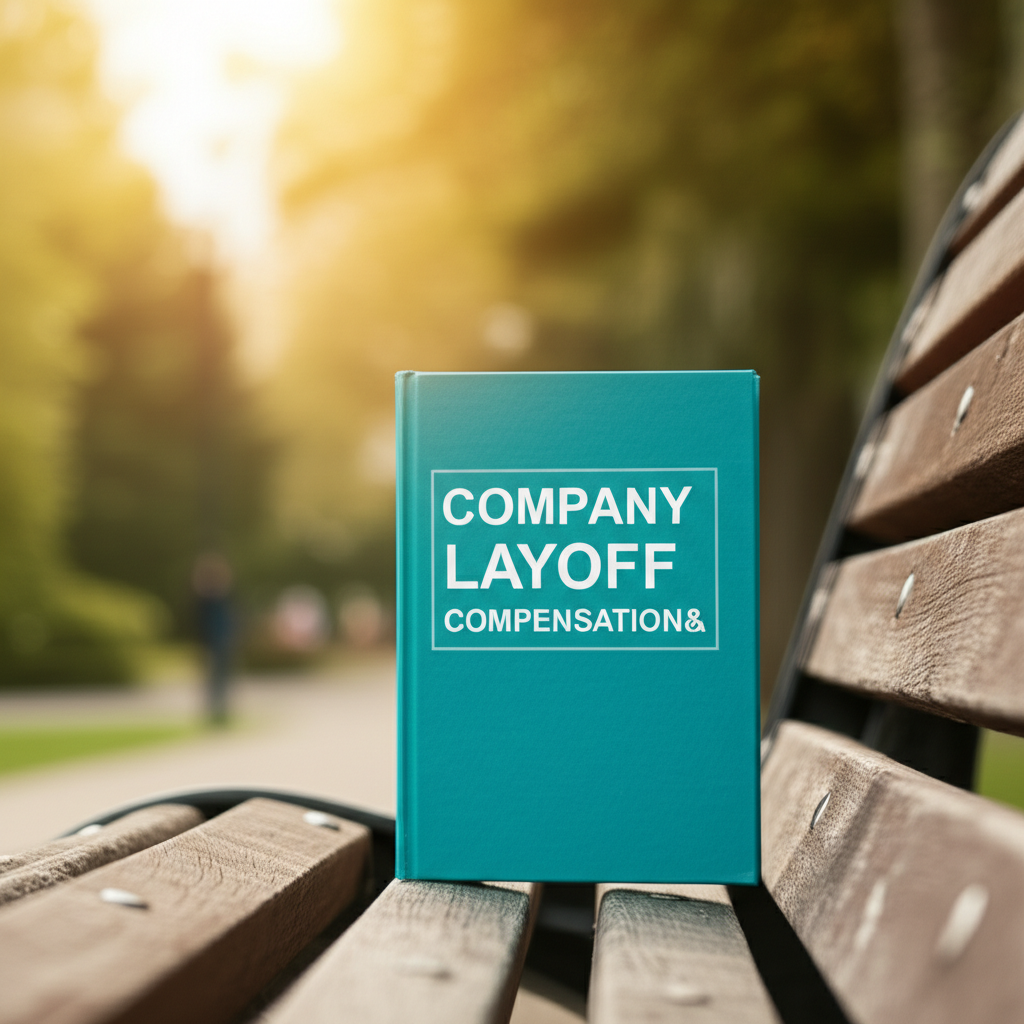会社都合退職は、突然のことで将来への不安を感じやすいものです。
特に、生活を支えるための補償金について、受け取れるのか、いくらもらえるのかなど、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、会社都合退職における補償金について、受給条件、計算方法、申請手順を徹底解説します。
会社都合退職の定義から、自己都合退職との違い、具体的なケースまで、基礎知識をわかりやすく解説。
補償金に関する疑問を解消し、スムーズな受給をサポートします。

会社都合退職の場合、必ず補償金はもらえるんですか?

補償金は、会社との合意や労働契約に基づいて支払われるため、まずは状況を確認し、会社と交渉することが大切です。
この記事でわかること
- 会社都合退職の定義
- 補償金受給の条件
- 補償金の計算方法
- 申請の手順
会社都合退職とは?補償金受給の基礎知識

会社都合退職は、会社側の都合で労働契約が終了することです。
補償金を受け取るためには、会社都合退職となる正当な理由を知っておくことが重要です。
ここでは、会社都合退職の定義、自己都合退職との違い、会社都合退職となる具体的なケースについて解説します。
これらの基礎知識を理解することで、会社都合退職の際に適切な判断と行動ができるようになります。
会社都合退職の定義
会社都合退職とは、会社の倒産や解雇など、会社側の事情によって労働者が退職せざるを得ない状況を指します。
会社都合退職は、労働者の意思とは関係なく、企業側の都合で雇用契約が終了する点が特徴です。

会社都合退職は、労働者の責任ではない理由で職を失うため、自己都合退職よりも手厚い保障が受けられる場合があります。
自己都合退職との違い
会社都合退職と自己都合退職の主な違いは、失業保険の受給条件です。
会社都合退職の場合、自己都合退職に比べて、失業保険の給付が早く、給付期間も長くなります。
| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 退職理由 | 会社の倒産、解雇、事業縮小など | 転職、結婚、育児、介護など |
| 失業保険の受給開始 | 7日間の待機期間後、すぐに支給開始 | 7日間の待機期間に加え、2〜3ヶ月の給付制限期間あり |
| 失業保険の給付日数 | 自己都合退職よりも長い | 会社都合退職よりも短い |
| 退職金の支給額 | 自己都合退職よりも優遇されている場合が多い | 会社都合退職よりも少ない場合がある |
会社都合退職となるケース
会社都合退職となるケースは、会社の倒産や解雇が一般的です。
その他にも、事業所の廃止や移転、労働条件の著しい相違、賃金未払い、ハラスメントなども会社都合退職と認められる場合があります。
| 会社都合退職のケース | 詳細 |
|---|---|
| 倒産 | 会社が経営破綻し、事業を継続できなくなった場合 |
| 解雇 | 会社が従業員の能力不足や業績不振などを理由に、一方的に雇用契約を解除する場合 |
| 事業所の廃止・移転 | 会社が事業所を閉鎖または移転し、従業員の通勤が困難になった場合 |
| 労働条件の著しい相違 | 採用時の労働条件と実際の労働条件が大きく異なり、従業員が退職せざるを得ない場合 |
| 賃金未払い | 会社が従業員に賃金を支払わない、または大幅に遅延させる場合 |
| ハラスメント | 会社内でパワーハラスメントやセクシャルハラスメントが発生し、従業員が就業を継続することが困難になった場合 |
補償金受給の条件と確認点
会社都合退職で補償金を受け取るには、会社都合退職であることの正当な理由が最も重要です。
そのほかの条件や確認点について、これから詳しく解説していきます。
ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
会社都合退職の正当な理由
会社都合退職と認められるには、倒産や解雇など、会社側の都合で退職せざるを得ない状況であったという正当な理由が求められます。
正当な理由があると認められるケースとして、下記のようなものが挙げられます。
| 会社都合退職の理由 | 内容 |
|---|---|
| 倒産 | 会社が経営破綻し、事業継続が不可能になった場合 |
| 事業所閉鎖・移転 | 会社が事業所を閉鎖、または移転し、通勤が困難になった場合 |
| 解雇(不当解雇を含む) | 会社から一方的に解雇された場合(解雇理由が客観的に合理的でなく、社会通念上相当と認められない場合を含む) |
| 退職勧奨 | 会社から退職を勧められ、それに応じた場合 |
| 労働条件の著しい相違 | 採用時に提示された労働条件と、実際の労働条件が著しく異なっていた場合(給与の未払いや大幅な減額、残業時間の著しい増加、ハラスメントなど) |
| その他、会社側の責めに帰すべき事由による退職 | 上記以外にも、会社側の問題(法令違反、安全配慮義務違反など)が原因で退職せざるを得なくなった場合 |

会社都合で退職したはずなのに、自己都合退職として扱われそう…

会社都合退職であることの証拠を集め、ハローワークに相談しましょう。
会社との交渉姿勢
補償金を受け取るためには、会社に対して補償金の支払いを求める交渉を行う姿勢が重要です。
会社側から提示された条件を鵜呑みにせず、自身の権利を主張することが大切です。
交渉を有利に進めるためには、以下の点を意識しましょう。
- 証拠の収集: 会社都合退職となった経緯を証明できる資料(解雇通知、退職勧奨の記録、労働条件通知書など)を収集する
- 弁護士への相談: 法的な観点からアドバイスを受け、交渉を有利に進めるための戦略を立てる
- 第三者の介入: 労働組合や労働基準監督署など、第三者の機関に相談し、交渉の仲介を依頼する
合意書の内容確認
会社から補償金の支払いを含む合意書の提示があった場合、内容を十分に確認することが不可欠です。
合意書にサインしてしまうと、後から内容を覆すことが難しくなるため、慎重に判断しましょう。
合意書を確認する際のポイントは以下の通りです。
- 補償金額: 金額が自身の状況や退職理由に見合ったものであるかを確認する
- 支払い時期と方法: いつ、どのような方法で支払われるのかを確認する
- 清算条項: 合意書に記載された内容以外に、会社に対して一切の請求を行わないという文言が含まれていないかを確認する
- 秘密保持条項: 退職の経緯や合意内容について、口外しないことを義務付ける条項が含まれていないかを確認する
合意書の内容に不明な点や納得できない点がある場合は、必ず会社に説明を求め、必要に応じて修正を依頼しましょう。
弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることも有効です。
補償金の相場と計算方法
会社都合退職における補償金の相場は、個別の状況や交渉によって大きく変動する点が重要です。
補償金の計算例
補償金の計算例は、月額給与を基準として算出されるケースが多いです。
たとえば、基本給の3ヶ月分、6ヶ月分、あるいはそれ以上の金額が提示されることがあります。

補償金って、具体的にどうやって計算されるんだろう?

月額給与を基準に、勤続年数や退職理由などを考慮して算出されることが多いよ。
年齢・勤続年数の影響
補償金の額は、年齢や勤続年数が長いほど高くなる傾向にあります。
これは、長年会社に貢献してきた従業員に対する慰労の意味合いや、再就職の難易度を考慮するためです。
| 項目 | 影響 |
|---|---|
| 年齢 | 高齢であるほど、再就職が難しくなるため、補償金が高くなる傾向 |
| 勤続年数 | 長いほど、会社への貢献度が高いとみなされ、補償金が高くなる傾向 |
| 役職 | 役職が高いほど、責任が重く、再就職が難しくなるため、補償金が高くなる傾向 |
| 退職理由 | 会社都合の度合いが高いほど、補償金が高くなる傾向 |
| 交渉力 | 弁護士などを通じて交渉することで、補償金が増額される可能性 |
弁護士による計算
弁護士に依頼した場合、法的な観点から適切な補償金額を算出し、会社との交渉を代行してもらうことが可能です。
弁護士は、過去の判例や労働法に基づいて、依頼者の権利を最大限に守るためのサポートを行います。
補償金の申請手順と注意点
会社都合退職における補償金の申請は、会社との交渉から始まり、税金や社会保険に関する注意点まで、いくつかのステップを踏む必要があります。
それぞれの段階で適切な対応をすることで、スムーズな申請と受給を目指せるでしょう。
会社との交渉
会社との交渉は、補償金を得るための最初のステップであり、非常に重要な過程です。
ここでは、冷静かつ論理的に自身の状況を伝え、会社側の理解を得ることが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交渉の準備 | 退職理由が会社都合であることを明確にする証拠(解雇通知、退職勧奨の記録など)を集めておく |
| 交渉の進め方 | 感情的にならず、客観的な事実に基づいて交渉を進める。弁護士などの専門家を同席させることも検討する |
| 交渉のポイント | 自身の希望する補償金額や条件を明確に伝える。合意に至った場合は、必ず書面(合意書)を作成する |
| 注意点 | 口約束は避ける。交渉の過程で不利な発言をしないように注意する |
弁護士への相談
弁護士への相談は、法的な観点から交渉を有利に進めるために有効な手段です。
専門家のアドバイスを受けることで、自身の権利を守りながら、より良い条件での合意を目指せます。

弁護士に相談するのって、ハードルが高い気がする…

弁護士はあなたの味方です。法律の専門家として、あなたの権利を守るためにサポートしてくれます。
弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
- 法的なアドバイス: 会社との交渉において、法的に有効な主張や証拠の収集方法についてアドバイスを受けられる。
- 交渉の代行: 弁護士が代わりに会社と交渉することで、精神的な負担を軽減できる。
- 合意書の作成: 合意内容を法的に有効な書面にまとめることで、後々のトラブルを防止できる。
税金と社会保険
補償金は、税金や社会保険の対象となる場合があるため、注意が必要です。
受給後の手続きや影響を事前に確認しておくことで、将来的な経済的な負担を軽減できます。
税金や社会保険に関する注意点は以下の通りです。
- 税金: 補償金は、所得税の課税対象となる場合があります。税務署や税理士に相談し、確定申告の手続きを行うようにしましょう。
- 社会保険: 補償金の受給により、社会保険料の負担が増える可能性があります。社会保険事務所や年金事務所に相談し、影響を確認しておきましょう。
会社都合退職に伴う補償金の申請は、複雑な手続きを伴う場合がありますが、各ステップを理解し、適切な対応を行うことで、スムーズな受給と将来の安心につながります。
会社都合退職後の生活設計
会社都合退職後の生活設計で最も重要なことは、経済的な安定を確保することです。
失業期間中の収入源を確保し、再就職までの生活を維持できるように、以下の項目では失業保険の受給、再就職支援サービスの活用、資金計画の立て方について解説します。
失業保険の受給
失業保険とは、雇用保険の被保険者が失業した場合に、生活の安定と再就職の促進のために支給される給付金です。
会社都合退職の場合、自己都合退職よりも受給要件が緩和され、給付日数も多くなるため、積極的に活用しましょう。
| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 受給要件 | 離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上あること | 離職日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること |
| 待機期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限 | なし | 原則として3か月(倒産・解雇等の場合は給付制限なし) |
| 給付日数 | 年齢や雇用保険の加入期間によって異なる(最大330日) | 年齢や雇用保険の加入期間によって異なる(最大150日) |
| 受給開始時期 | 待機期間満了後、すぐに受給開始 | 待機期間と給付制限期間満了後、受給開始 |

会社都合退職でも、失業保険がもらえない場合があるの?

雇用保険の加入期間が短い場合や、働く意思がない場合は受給できないことがあります。
再就職支援サービスの活用
再就職支援サービスとは、求職者に対して、求人情報の提供や職業相談、職業訓練などの支援を行うサービスのことです。
ハローワークや民間の転職エージェントなどが提供しており、無料で利用できるものもあります。
| サービス名 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 国が運営する職業安定所。全国各地に設置されており、求人情報の提供や職業相談、職業訓練などを行っている | 幅広い求人情報を扱っており、地域に密着した支援が受けられる |
| 民間の転職エージェント | 民間の企業が運営する転職支援サービス。求職者の希望やスキルに合わせた求人情報の提供や、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策などを行っている | 専門的な知識やノウハウを持っており、手厚いサポートが受けられる |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 国が運営する再就職支援機関。職業訓練や能力開発支援などを行っている | 専門的な知識やスキルを習得するための職業訓練が充実している |
| 地方自治体の再就職支援 | 地方自治体が独自に提供する再就職支援サービス。地域に特化した求人情報の提供や、セミナーや相談会などを開催している | 地域に密着した支援が受けられる |
| 労働組合 | 労働組合が組合員向けに提供する再就職支援サービス。求人情報の提供や職業相談、職業訓練などを行っている | 組合員同士のネットワークを活用した情報交換や支援が受けられる |
資金計画の立て方
会社都合退職後の生活を安定させるためには、失業保険の受給や再就職活動と並行して、資金計画を立てることが重要です。
収入と支出を把握し、無駄な支出を削減することで、生活費を確保することができます。
- 収入を把握する
- 失業保険の給付額
- 退職金や企業年金
- 貯蓄
- 家族からの援助
- 支出を把握する
- 住居費
- 食費
- 光熱費
- 通信費
- 保険料
- 交通費
- 娯楽費
- 資金計画を作成する
- 収入と支出を比較し、毎月の収支を計算する
- 不足する場合は、支出を削減するか、収入を増やすことを検討する
- 貯蓄を取り崩す場合は、計画的に行う
会社都合退職後の生活設計では、失業保険の受給、再就職支援サービスの活用、資金計画の立て方が重要です。
これらの対策を講じることで、経済的な安定を確保し、再就職に向けて前向きに進むことができます。
よくある質問(FAQ)
- 会社都合退職の場合、補償金は必ずもらえるのですか?
-
会社都合退職だからといって、必ず補償金がもらえるわけではありません。
補償金は、会社との合意や労働契約、就業規則に基づいて支払われるものです。
まずは、ご自身の状況を確認し、会社と交渉することが大切です。
- 会社から自己都合退職を勧められていますが、従うべきでしょうか?
-
会社から自己都合退職を勧められた場合でも、安易に従うべきではありません。
退職理由が会社都合に該当する場合は、その旨を会社に伝え、会社都合退職として扱ってもらうように交渉しましょう。
- 補償金の交渉は、自分で行うべきでしょうか?
-
補償金の交渉は、ご自身で行うことも可能ですが、弁護士や労働組合などの専門家に相談することも有効です。
専門家は、法的な知識や交渉のノウハウを持っており、あなたの権利を守り、より有利な条件で合意できるようサポートしてくれます。
- 補償金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?
-
補償金は、所得税の課税対象となる場合があります。
受け取った補償金の種類や金額によって、確定申告が必要かどうかが異なりますので、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
- 会社都合退職後、すぐに再就職が決まらない場合はどうすれば良いでしょうか?
-
会社都合退職後、すぐに再就職が決まらない場合は、失業保険を受給しながら、ハローワークや転職エージェントなどを活用して、積極的に求職活動を行いましょう。
また、職業訓練を受講することで、スキルアップを図り、再就職の可能性を高めることもできます。
- 会社都合退職後の生活費が不安です。利用できる制度はありますか?
-
会社都合退職後の生活費が不安な場合は、失業保険の他に、住居確保給付金や生活福祉資金貸付制度など、利用できる制度があります。
これらの制度は、一定の条件を満たす場合に、生活費や住居費の支援を受けることができるものです。
詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
まとめ
会社都合退職における補償金は、将来の生活を左右する重要な要素です。
この記事では、会社都合退職における補償金について、受給条件から申請方法、退職後の生活設計まで、必要な情報を網羅的に解説します。
- 会社都合退職の定義と自己都合退職との違い
- 補償金受給のための条件と交渉のポイント
- 補償金の相場と計算方法
- 会社都合退職後の生活設計
この記事を参考に、会社都合退職後の経済的な不安を解消し、次のステップへ進むための準備を始めましょう。