退職後の健康保険、どうすればいいか悩んでいませんか? 健康保険の任意継続は、退職後も会社の健康保険を継続できる制度で、選択肢の一つとして知っておくことが大切です。
手続きや条件を理解しておくことで、ご自身の状況に合わせた最適な選択ができます。
この記事では、任意継続の手続き、加入条件、保険料、国民健康保険との比較について詳しく解説します。
退職後の健康保険選びで迷わないように、ぜひ参考にしてください。

退職後の健康保険、どう選べばいいの?

この記事を読めば、あなたに合った選択肢が見つかります。
- 任意継続の手続きと条件
- 保険料の計算方法と国民健康保険との比較
- 任意継続のメリット・デメリット
- 任意継続の手続きを進める方法
健康保険任意継続制度の概要

健康保険任意継続制度とは、退職後も一定期間、会社の健康保険に継続して加入できる制度です。
退職後の健康保険を選ぶ上で、重要な選択肢の一つと言えるでしょう。
任意継続制度の利用を検討する際には、ご自身の状況に合わせて他の健康保険制度と比較し、最適な選択をすることが大切です。
本見出しでは、健康保険の種類と、それぞれの制度における加入条件や保険料について解説します。
退職後の健康保険選びは、将来の生活設計にも影響を与える重要な決断です。
それぞれの制度を理解し、納得のいく選択を行いましょう。
会社員が加入する健康保険
会社員は、原則として会社の健康保険に加入します。
加入する健康保険の種類は、企業の規模や業種によって異なります。
| 健康保険の種類 | 概要 |
|---|---|
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 中小企業を中心に、多くの方が加入する健康保険です。 |
| 健康保険組合 | 大企業や同業種の企業が集まって設立した健康保険です。協会けんぽよりも給付が充実している場合があります。 |
| 共済組合 | 公務員や教職員などが加入する健康保険です。 |
会社員として健康保険に加入している間は、保険料の一部を会社が負担してくれるため、自己負担額を抑えることが可能です。

会社を辞めたら、今まで加入していた健康保険はどうなるの?

退職後は、会社の健康保険から脱退することになります。
退職後の健康保険制度選択肢
会社を退職すると、会社の健康保険から脱退することになります。
退職後の健康保険制度の選択肢は、主に以下の3つです。
| 健康保険制度 | 概要 |
|---|---|
| 任意継続被保険者制度 | 退職後も、最長2年間、会社の健康保険に継続して加入できる制度です。 |
| 国民健康保険 | 市区町村が運営する健康保険で、自営業者や無職の方などが加入します。 |
| 家族の健康保険の被扶養者になる | 家族が加入している健康保険の被扶養者となることで、保険料を支払うことなく健康保険に加入できます。 |
退職後の健康保険を選ぶ際には、ご自身の状況や将来のライフプランに合わせて、最適な制度を選ぶことが大切です。
保険料や給付内容、加入条件などを比較検討し、慎重に判断しましょう。
任意継続の手続きと条件

退職後の健康保険として任意継続を選択する場合、加入条件や手続きの流れを理解しておくことが重要です。
任意継続の手続きは期限があるため、この記事では、加入条件、手続きの流れ、保険料、国民健康保険との比較検討ポイントを解説します。
自身にとって最適な選択をするために、具体的な情報を確認していきましょう。
任意継続被保険者の加入条件
任意継続被保険者になるには、退職日までに一定の条件を満たしている必要があります。
加入条件を満たしていない場合、任意継続の手続きはできません。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 退職日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること |
| 手続き期限 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請すること |
| 年齢 | 75歳未満であること(75歳以上は後期高齢者医療制度に加入するため) |
| その他 | 日本国内に住所を有すること |
任意継続の手続きの流れ
任意継続の手続きは、期限内に必要な書類を準備して提出する必要があります。
手続きが遅れると任意継続ができなくなる可能性があるため、流れを把握してスムーズに進めましょう。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1.書類準備 | 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を準備する。 |
| 2.提出 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、加入していた健康保険組合に提出する。 |
| 3.審査 | 健康保険組合による審査が行われる。 |
| 4.保険料納付 | 審査通過後、健康保険組合から納付書が送付されるので、期日までに保険料を納付する。 |
| 5.加入 | 保険料納付後、任意継続被保険者証が交付され、任意継続被保険者となる。 |
任意継続の保険料と期間
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。
また、加入期間は最長で2年間となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料 | 退職時の標準報酬月額を基に算出、全額自己負担 |
| 加入期間 | 最長2年間 |
| 保険料変更 | 原則として加入期間中は変わらない。ただし、40歳で介護保険第2号被保険者になった場合や、健康保険料率が変更された場合などは変更される。 |
国民健康保険との比較検討ポイント
退職後の健康保険は、任意継続と国民健康保険のどちらかを選択できます。
保険料や保障内容、加入期間などを比較して、自分に合った方を選びましょう。
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 保険料 | 退職時の標準報酬月額を基に算出、全額自己負担 | 前年の所得に基づいて算出、全額自己負担、所得によって変動 |
| 加入期間 | 最長2年間 | 期間制限なし |
| 扶養家族 | 退職前と同じ扶養家族が継続加入可能 | 個別に国民健康保険に加入が必要 |
| メリット | 扶養家族がいる場合は保険料を抑えられる場合がある、在職中の健康保険の独自給付を継続して受けられる可能性がある | 退職後の減収に応じて保険料が下がる可能性がある、加入期間に制限がない |
| デメリット | 保険料が全額自己負担、加入期間が最長2年間、出産手当金や傷病手当金は給付されない | 退職後1年目の収入が増加した場合、翌年の保険料が上がる可能性がある、扶養家族も個別で国民健康保険に加入する必要がある |
任意継続を選択するメリット・デメリット

任意継続被保険者制度は、退職後の健康保険として重要な選択肢です。
保険料や扶養家族の有無など、ご自身の状況に合わせて最適な選択をすることが大切です。
以下に、任意継続を選択するメリット・デメリットをまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせながら、どちらが適しているか検討する際の参考にしてください。
任意継続のメリット
任意継続のメリットは、退職後もこれまで加入していた健康保険を継続できる点です。

任意継続にすると何が良いんだろう?

任意継続のメリットは、今までと同じ保険内容を継続できる安心感があることです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険内容の継続 | 在職中と同様の給付内容(傷病手当金や出産手当金など)が受けられる可能性がある |
| 扶養家族 | 引き続き被扶養者として健康保険に加入できる |
| 手続きの簡便さ | 退職手続きと並行して行える場合がある |
| 高額療養費の自己負担限度額 | 所得に応じて自己負担限度額が決まるため、高額な医療費がかかった場合でも安心できる |
任意継続のデメリット
任意継続のデメリットは、保険料が全額自己負担になる点です。

保険料はどのくらいになるの?

退職時の標準報酬月額を基に計算されるため、在職中よりも保険料が高くなる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料の負担 | 全額自己負担となるため、在職中よりも負担が増える |
| 加入期間の制限 | 最長2年間しか加入できない |
| 給付制限 | 出産手当金や傷病手当金は原則として支給されない |
| 保険料の滞納 | 1日でも滞納すると資格を失う |
| 保険料の変更の可能性 | 40歳で介護保険第2号被保険者になった場合や、保険料率が変更された場合など、保険料が変更される可能性がある |
任意継続がおすすめなケース
任意継続は、以下のようなケースにおすすめです。

どんな人が任意継続に向いているの?

扶養家族が多い方や、退職後も手厚い保障を継続したい方におすすめです。
| ケース | おすすめ理由 |
|---|---|
| 扶養家族がいる場合 | 国民健康保険では扶養家族分の保険料もかかるため、任意継続の方が保険料を抑えられる可能性がある |
| 退職後も手厚い保障が必要な場合 | 傷病手当金や出産手当金など、在職中と同様の給付を受けられる可能性がある(ただし、受給条件を満たす必要あり) |
| 国民健康保険料が高い場合 | 退職時の標準報酬月額によっては、国民健康保険よりも任意継続の方が保険料が安くなる場合がある |
| 加入条件を満たしている場合 | 退職日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要がある |
受け取り損ねていませんか?
退職後のサポートとして知られる「失業給付金」ですが、
制度をよく知らないまま受け取れていない人が多いのをご存じでしょうか?
実際、内閣府の資料によると、
失業者のうち実際に失業給付(基本手当)を受けているのは
全体の2〜3割程度にすぎません。
「知らなかった…」というだけで、本来もらえるはずの
給付金を逃してしまっている人がたくさんいるのです。
- ✅ 退職を考えている/すでに退職した
- ✅ 体調不良・メンタル不調でやむを得ず辞めた
- ✅ 契約満了・派遣・パートなど非正規で終了した
- ✅ 失業保険や給付金の制度をよく知らない
- ✅ 「自分も対象なのか?」知っておきたい
「退職したら失業保険がもらえる」
実は、申請の方法やタイミングによって
受け取れる金額が大きく変わることをご存じですか?
たとえば、同じように退職した2人でも…
Aさん:調べずに自己都合で退職 → 約58万円の受給
Bさん:制度を理解して申請 → 約148万円の受給
この差は、「知っていたかどうか」だけなのです。
でも安心してください。
今からでも、正しい知識を知ることで
あなたも損をせずに受け取れる可能性があります。
難しい手続きも、まずは簡単な無料診断で
「自分が対象かどうか」をチェックすることから始めましょう。
申請次第で100万円以上変わるかもしれません。
任意継続の手続きを進める方法
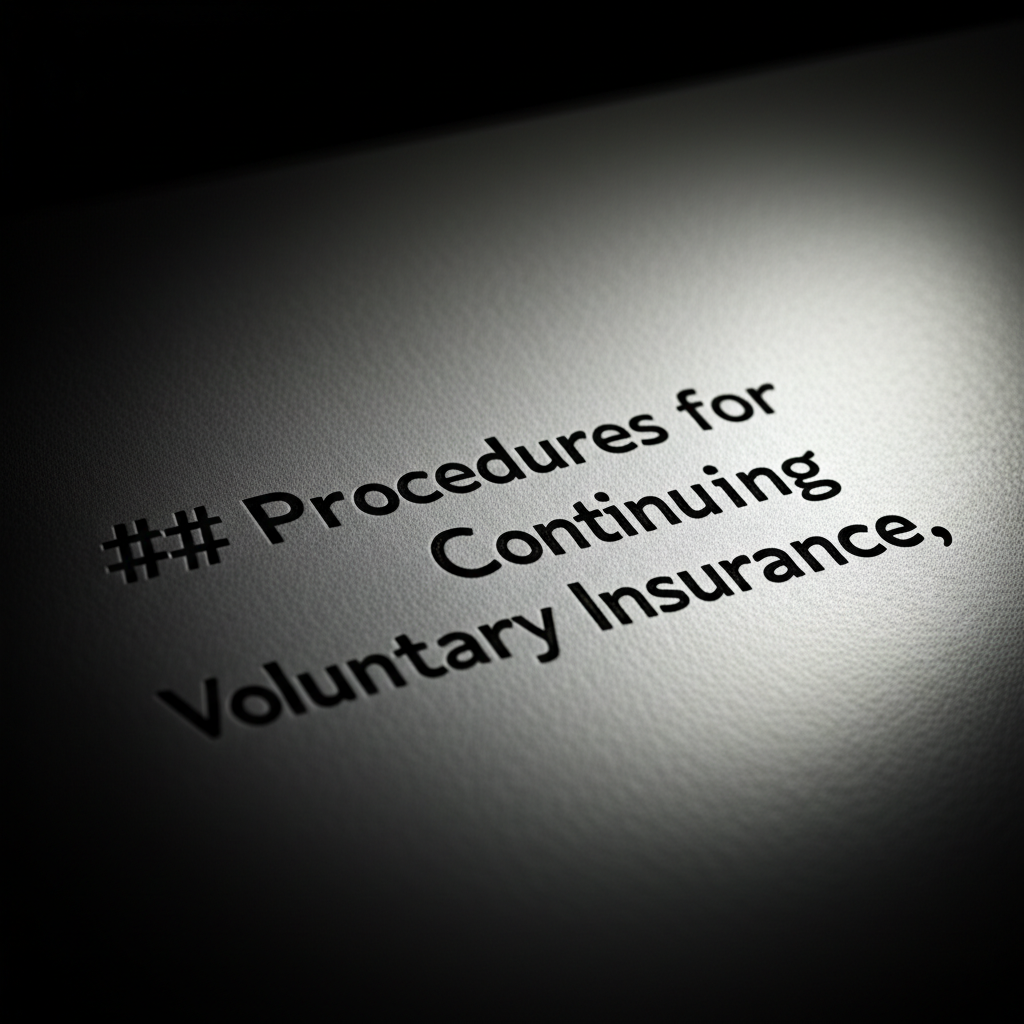
退職後の健康保険を任意継続するためには、期限内に必要な書類を準備し、提出する必要があります。
以下に、手続きのステップを具体的に解説します。
各ステップをしっかり確認し、スムーズな手続きを進めましょう。
健康保険任意継続資格取得申請書の準備
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」は、任意継続を始めるために最も重要な書類です。
申請書は、全国健康保険協会のWebサイトからダウンロードできる他、会社の健康保険担当部署や社会保険事務所でも入手できます。

申請書の入手方法がわからない…

まずは会社の担当部署に問い合わせてみましょう。
申請書には、以下の情報を正確に記入する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 自身の氏名を記入します |
| 生年月日 | 自身の生年月日を記入します |
| 住所 | 自身の住所を記入します |
| 電話番号 | 連絡が取れる電話番号を記入します |
| 資格喪失日 | 健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)を記入します |
| 任意継続被保険者希望年月日 | 任意継続を希望する年月日(資格喪失日の翌日)を記入します |
| 署名・捺印 | 申請者本人が署名・捺印します |
申請書は楷書で丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意しましょう。
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書の提出先
申請書の提出先は、加入していた健康保険によって異なります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ提出します。

どこに提出すればいいの?

協会けんぽのWebサイトで管轄の支部を確認しましょう。
提出方法は、以下のいずれかを選択できます。
| 提出方法 | 詳細 |
|---|---|
| 郵送 | 申請書と必要書類を封筒に入れ、郵送します。 |
| 窓口 | 管轄の協会けんぽの窓口に直接提出します。 |
提出期限は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。
期限を過ぎると任意継続ができなくなるため、早めに手続きを行いましょう。
郵送の場合は、消印有効となるため、期限内に発送するように注意が必要です。
健康保険任意継続後の保険料納付方法
任意継続の保険料は、原則として毎月納付する必要があります。
納付方法は、以下のいずれかを選択できます。
| 納付方法 | 詳細 |
|---|---|
| 口座振替 | 事前に口座振替の手続きを行うことで、自動的に保険料が引き落とされます。 |
| 納付書 | 協会けんぽから送付される納付書を使用し、金融機関やコンビニエンスストアで支払います。 |
保険料は、毎月10日までに納付する必要があります。
納付期限を過ぎると、督促状が送付され、最悪の場合は任意継続の資格を失ってしまう可能性があります。
口座振替を選択した場合は、引き落とし日に口座残高が不足しないように注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
- 退職後、すぐに任意継続の手続きをしないといけませんか?
-
はい、任意継続被保険者になるためには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請する必要があります。
期限を過ぎると、任意継続の手続きができなくなるのでご注意ください。
- 任意継続の保険料は、どのように決まりますか?
-
任意継続の保険料は、原則として退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。
ただし、保険料には上限額があり、加入期間中に健康保険料率が変更された場合は、保険料が変更されることがあります。
- 任意継続と国民健康保険では、どちらが保険料が安くなる可能性がありますか?
-
一般的に、退職後の収入が大幅に減る場合は国民健康保険の方が保険料が安くなる可能性があります。
しかし、扶養家族がいる場合や、退職時の標準報酬月額によっては、任意継続の方が保険料を抑えられる場合もあります。
ご自身の状況に合わせて比較検討することが重要です。
- 任意継続の加入期間はどのくらいですか?
-
任意継続の加入期間は、最長で2年間です。
2年経過後は、国民健康保険への切り替えが必要になります。
ただし、75歳になった場合は、後期高齢者医療制度への加入が必要です。
- 任意継続中に再就職した場合、どうすれば良いですか?
-
任意継続中に再就職し、会社の健康保険に加入した場合は、任意継続の資格喪失手続きを行う必要があります。
再就職先の健康保険証のコピーなどを添えて、加入していた健康保険組合に資格喪失の届け出をしてください。
- 任意継続の保険料を滞納すると、どうなりますか?
-
任意継続の保険料を滞納すると、資格を失うことがあります。
保険料は必ず納付期限までに納めるようにしましょう。
もし納付が難しい場合は、早めに加入していた健康保険組合に相談してください。
まとめ
退職後の健康保険として、健康保険の任意継続は重要な選択肢です。
この記事では、任意継続の手続きや条件、国民健康保険との比較について詳しく解説し、最適な選択をサポートします。
- 任意継続の手続きと条件
- 保険料の計算方法と国民健康保険との比較
- 任意継続のメリット・デメリット
退職後の健康保険選びで迷わないように、この記事を参考に、ご自身の状況に合った最適な選択をしてください。
「退職したら失業保険もらえるでしょ…」
そう思って辞めた人、けっこう後悔してます。
- ✅ 自己都合でも最短7日で受給スタート
- ✅ 10万円〜170万円以上もらえた事例も
- ✅ 成功率97%以上の専門サポート付き
通院歴やメンタル不調のある方は
むしろ受給率が上がるケースも。
・26歳(勤続 2年)月収25万円 → 約115万円
・23歳(勤続 3年)月収20万円 → 約131万円
・40歳(勤続15年)月収30万円 → 約168万円
・31歳(勤続 6年)月収35万円 → 約184万円
※受給額は申請条件や状況により異なります
※退職済みの方も申請できる場合があります
