太陽光発電システムの導入を検討する中で、高額な初期費用が大きな負担になっていませんか? 福岡市では、環境にも家計にも優しい住宅用エネルギーシステムの導入を支援する補助金制度があります。
この補助金制度は、太陽光発電や蓄電池などの設置費用を大幅に抑え、電気代の高騰に負けない経済的な暮らしを実現するための重要な支援策です。
最大100万円以上お得になる可能性もあり、地球温暖化対策にも貢献できる、まさに「一石二鳥」のチャンスと言えます。
- 令和7年度の補助金制度の全体像
- 対象となるシステムと具体的な交付額
- 申請から受領までの手続きと注意点
- 他の補助金との併用メリット
福岡市住宅用エネルギー支援事業とは

福岡市が地球温暖化対策と持続可能な社会の実現のために実施している「令和7年度住宅用エネルギーシステム導入支援事業」は、太陽光発電などの再生可能エネルギー導入を検討しているみなさんにとって、初期費用を賢く抑え、家計と環境に優しい生活を実現できる大変重要な機会です。
私自身も補助金の情報は「もっと早く知りたかった」と後悔することがありましたから、みなさんにはこの情報を最大限に活用していただきたいと考えます。
この支援事業は、福岡市が掲げる事業の「目的と支援の意義」から始まり、具体的な「令和7年度の予算と受付期間」、そして補助金を活用することによる「経済的メリット」といった全体像を理解することで、より深く制度を使いこなせるでしょう。
福岡市が提供するこの支援事業は、単なる補助金の支給だけでなく、市民一人ひとりの環境意識を高め、より持続可能な都市づくりに貢献することを目指しています。
ぜひこの制度を活用し、未来を見据えたスマートなエネルギー選択に踏み出してほしいです。
それでは、各見出しで詳細をご案内します。
事業の目的と支援の意義
「福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業」は、福岡市が地球温暖化対策と持続可能な社会の実現を目指して、市民の暮らしをサポートする制度です。
具体的には、家庭での自家消費型システムの普及、再生可能エネルギーの導入促進、そしてエネルギー全体の省エネルギー化の推進を目的としています。
2024年の福岡市は年間約2,236時間の日照と4.02Wh/㎡の日射量があり、1kWあたり年間約1247.2kWhの発電量が見込まれます。
太陽光発電導入により、電力会社から購入する電気を減らし、環境への負荷も軽減できるため、非常に効果的な取り組みです。
本事業の主な目的
- 自家消費型システムの普及
- 再生可能エネルギーの導入促進
- エネルギー全体の省エネルギー化推進

具体的に、どのような環境効果があるのか気になります。

温室効果ガスの排出を抑え、クリーンなエネルギー利用を促進することにつながります。
この支援事業は、福岡市が環境への配慮と市民生活の質の向上を両立させるために重要な役割を果たしています。
エネルギーの自給自足を目指し、未来に貢献できる素晴らしい機会です。
令和7年度の予算と受付期間
補助金申請において最も重要な情報の一つが、受付期間と予算の動向です。
これらは、みなさんが申請計画を立てる上で直接影響します。
令和7年度の福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業は、総額2億6,950万円の予算が確保されています。
申請受付期間は令和7年5月7日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までとなっていますが、予算がなくなり次第、受け付けは終了です。
過去の補助金制度を見ても、予算消化は想定より早いことがあります。
私からは、年度の初め頃に申請が集中しやすいため、早めの情報収集と準備が成功の鍵です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助枠総額 | 2億6,950万円 |
| 申請受付期間 | 令和7年5月7日~令和8年1月30日 |
| 申請方法 | 電子メールまたは郵送 |

もし予算がなくなったら、申請はできなくなるのでしょうか。

予算がなくなり次第、その年度の申請は締め切られてしまうため、早めの行動が不可欠です。
申請は電子メールまたは郵送のみで受け付けています。
特に令和7年5月7日に電子メールで申請した書類の一部が受理できていない事例も報告されていますので、不安な場合は速やかに事務局に確認するようにしてください。
計画的に手続きを進め、この貴重な補助金獲得を目指しましょう。
補助制度活用の経済的メリット
福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業の補助金を活用することで、みなさんは設置費用の大幅な軽減という具体的な経済的メリットを享受できます。
太陽光発電や蓄電池などの再生可能エネルギーシステムは、初期投資が大きな負担となりがちですが、補助金によってその一部が助成されるため、導入へのハードルが大きく下がります。
例えば、住宅用太陽光発電システム(戸建)なら2万円/kW(上限10万円)、リチウムイオン蓄電システムなら機器費の2分の1(上限40万円)の補助が受けられます。
国や他の地方自治体の補助金との併用も可能で、組み合わせ次第では最大100万円以上お得になる可能性も秘めている制度です。
補助金による経済的恩恵
- 初期費用の負担軽減
- 長期的な電気代の削減
- 他の補助金との併用でさらにお得になる可能性

補助金がなくても太陽光発電を導入するメリットはあるのでしょうか。

設置費用は年々低下し、電気代は高騰傾向にあるため、自家消費による電気代削減効果は補助金がなくても十分に魅力的です。
電気代高騰の時代において、自宅で発電した電気を使うことは、家計の節約だけでなく、エネルギーの自給自足にもつながります。
福岡市の補助金制度を賢く活用し、安心で経済的なエコライフをぜひ手に入れてください。
補助対象システムの詳細と交付額

福岡市が推進する「令和7年度住宅用エネルギーシステム導入支援事業」を最大限に活用するには、対象となるシステムの具体的な種類、それぞれの要件、そして交付される補助金額を正確に把握することが不可欠です。
補助金は、初期投資の負担を大きく軽減し、みなさんのエコな暮らしを後押しする重要な支援策ですが、その詳細を理解していなければ、せっかくの機会を逃してしまう可能性もあります。
導入を検討しているシステムが本当に補助の対象となるのか、いくら補助してもらえるのかといった疑問を解消するために、ここでは各システムを詳しく解説し、みなさんの不安を解消します。
ここでは、まず単体補助と組み合わせ補助という二つの基本的な補助区分を明確にします。
次に、戸建住宅向けと集合住宅向けに異なる太陽光発電システムの条件を掘り下げます。
そして、蓄電システム、V2Hシステム、高効率給湯器、家庭用燃料電池といったその他の主要な補助対象システムそれぞれの要件と、導入時に確認すべき具体的なポイントを解説します。
最終的に、各システムごとの具体的な補助交付額と、補助金の上限や端数処理のルールを確認し、正確な申請準備を整えるお手伝いをします。
導入を検討しているシステムの詳細な要件と、それに応じた補助金額をしっかり把握することが、計画を立てる上での重要な出発点となります。
単体補助と組み合わせ補助
補助金制度には、システムを単独で導入する「単体補助」と、複数のシステムを組み合わせて導入する「組み合わせ補助」の二種類の区分があります。
この二つの違いを理解することは、ご自身の導入計画に最適な補助区分を選択するために非常に重要です。
特に、補助対象となるシステムの種類や組み合わせ方に注意を払い、それぞれの要件を正しく把握する必要があります。
単体補助では、住宅用太陽光発電システム(集合住宅向け)または家庭用燃料電池のいずれかを単独で設置する場合に適用されます。
家庭用燃料電池を単体で導入できるのは200件までと上限が設定されています。
一方で、組み合わせ補助は、住宅用太陽光発電システム(戸建・集合住宅向け)、リチウムイオン蓄電システム、V2Hシステム、高効率給湯器、家庭用燃料電池といったシステムを、既設の太陽光発電システムやHEMS(家庭向けエネルギー管理システム)を含む特定の条件システムと組み合わせて導入する場合に適用されます。
ただし、高効率給湯器と家庭用燃料電池は、どちらか一方のみが補助対象となります。
| 補助区分 | 対象システム | 主な条件 |
|---|---|---|
| 単体補助 | 住宅用太陽光発電システム(集合住宅向け) | なし |
| 家庭用燃料電池 | 単体導入の上限200件 | |
| 組み合わせ補助 | 住宅用太陽光発電システム(戸建・集合住宅向け) | 既設太陽光発電システムまたはHEMSとの組み合わせ必須 |
| リチウムイオン蓄電システム | 既設太陽光発電システムまたはHEMSとの組み合わせ必須 | |
| V2Hシステム | 既設太陽光発電システムまたはHEMSとの組み合わせ必須 | |
| 高効率給湯器(エコキュート) | 既設太陽光発電システムまたはHEMSとの組み合わせ必須 | |
| 家庭用燃料電池 | 既設太陽光発電システムまたはHEMSとの組み合わせ必須 | |
| 注意 | 高効率給湯器と家庭用燃料電池はどちらか一方のみ補助対象 | 補助金利用可否の選択肢 |

複数のシステムを導入したいけれど、どちらの補助金が使えるのか迷ってしまうわ

ご自身の導入計画に合った補助区分を適切に選択することが重要です
単体補助と組み合わせ補助、どちらの区分が適用されるかによって、対象となるシステムや要件が異なります。
ご自身の導入計画に最適な補助区分を選びましょう。
戸建・集合住宅の太陽光システム
住宅用太陽光発電システムとは、屋根などに太陽光パネルを設置し、太陽の光エネルギーを電力に変換して家庭で利用するシステムのことです。
このシステムは、自家消費による電気料金の削減や、余剰電力の売電を通じて家計にメリットをもたらします。
福岡市では、戸建住宅と集合住宅のそれぞれで異なる補助金要件が設定されています。
太陽光発電システムを導入する際の共通要件として、電力系統に接続されていること、そして発電した電力を住居部分または共用部分で使用することが主な目的である必要があります。
特に、組み合わせ補助として太陽光発電システムを導入する場合、HEMS(家庭向けエネルギー管理システム)の設置が必須となります。
HEMSが既設の場合でもこの条件を満たします。
電力系統への接続や発電した電力を住居部分または共用部分で使用することが主な目的であり、組み合わせ補助を申請する場合はHEMSの設置が必須となります。
- 電力系統への接続: 必須
- 発電電力の用途: 住居部分または共用部分での使用が主な目的
- HEMS設置(組み合わせ補助の場合): 既設も可

太陽光発電システムを導入したいけれど、HEMSは必須なの?

組み合わせ補助を利用する場合は、HEMSの設置が必須となります
戸建住宅・集合住宅のいずれにおいても、福岡市の補助金を活用して太陽光発電システムを導入するには、HEMS設置など特定要件を満たす必要があります。
蓄電・V2H・高効率給湯器・燃料電池システム
太陽光発電システム以外にも、福岡市ではさまざまな住宅用エネルギーシステムの導入に対して補助金が提供されています。
これらは、エネルギーの自家消費率を高めたり、災害時の電力供給を確保したり、給湯や発電の効率を高めたりと、多岐にわたるメリットをもたらします。
それぞれのシステムが持つ機能と、補助金を受けるための具体的な要件を把握することが大切です。
リチウムイオン蓄電システムは、太陽光発電などでつくられた電気を貯めて必要な時に使うことで、電気料金の削減や停電時の備えになるシステムです。
補助対象となるのは、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が令和6年度以降に登録・公表する蓄電システムで、機器費が蓄電容量1kWhあたり13.5万円以下という基準があります。
V2Hシステムとは、電気自動車(EV)などに貯められた電力を家庭で利用するための設備を指し、停電時や日常の電力供給源として活用できます。
一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が補助対象V2H充放電設備一覧に掲載しているものであること、そして電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を保有(または購入予定)していることが要件です。
高効率給湯器(エコキュート)は、空気中の熱を利用してお湯を沸かす、省エネ性能に優れた給湯システムです。
CO2を冷媒として使用する空気熱源ヒートポンプ給湯器で、2025年度目標基準値以上の性能値を有するもの、またはおひさまエコキュートである必要があります。
家庭用燃料電池は、都市ガスなどから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電と給湯を行うクリーンなエネルギーシステムです。
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品が対象です。
- リチウムイオン蓄電システム:
- SIIが令和6年度以降に登録・公表するシステムであること
- 機器費が蓄電容量1kWhあたり13.5万円以下のシステムであること
- V2Hシステム:
- NeVが補助対象V2H充放電設備一覧に掲載されていること
- 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の保有または購入予定であること
- 高効率給湯器(エコキュート):
- CO2を冷媒として使用する空気熱源ヒートポンプ給湯器であること
- 2025年度目標基準値以上の性能値を有すること、またはおひさまエコキュートであること
- 家庭用燃料電池:
- FCAが公表する登録機器リストに登録されている製品であること

たくさんのシステムがあるけれど、それぞれに厳しい条件があるのね

各システムの詳細な基準を確認し、適合する製品を選ぶことが大切です
リチウムイオン蓄電システム、V2Hシステム、高効率給湯器、家庭用燃料電池のそれぞれに補助金が設定されていますが、適用には特定の公的リストへの登録や性能基準を満たす必要があります。
各システム別補助交付額一覧
福岡市が提供する「令和7年度住宅用エネルギーシステム導入支援事業」では、対象となる各システムの導入に対して具体的な補助交付額が設定されています。
システムの種類や導入形態(戸建・集合住宅)によって交付額は異なり、上限額も定められています。
自身の導入計画に合った補助額を正確に把握し、全体の費用計画を立てるために、この一覧表を参考にすることが重要です。
ここでは、各補助対象システムに対する具体的な交付額を明示します。
例えば、戸建住宅向けの太陽光発電システムには2万円/kW(上限10万円)が、集合住宅向けの太陽光発電システムには2万円/kW(上限60万円)が支給されます。
蓄電システムやV2Hシステムは機器費の2分の1が補助され、それぞれ40万円、20万円の上限があります。
高効率給湯器は定額2万円、家庭用燃料電池は定額5万円が交付されます。
特に集合住宅向けの太陽光発電システムは、最大60万円と手厚い支援を受けられます。
| 補助対象システム | 補助交付額 | 補助対象住宅 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム(戸建) | 2万円/kW(上限10万円) | 戸建住宅 |
| 住宅用太陽光発電システム(集合住宅) | 2万円/kW(上限60万円) | 集合住宅 |
| リチウムイオン蓄電システム | 機器費の2分の1(上限40万円) | 戸建住宅・集合住宅 |
| V2Hシステム | 機器費の2分の1(上限20万円) | 戸建住宅・集合住宅 |
| 高効率給湯器(エコキュート) | 定額2万円 | 戸建住宅・集合住宅 |
| 家庭用燃料電池 | 定額5万円(単体設置の場合上限200件) | 戸建住宅・集合住宅 |

私の家に設置するシステムの補助額が、具体的にいくらになるのか知りたいわ

導入するシステムと種類によって交付額が異なるため、この一覧表で確認してください
各システムで補助交付額の上限や算出方法が異なり、この一覧表を参考にしながら、自身の導入予定システムにおける具体的な補助金額を確認しましょう。
補助金上限と端数処理の確認
補助金の申請において、交付される金額には上限が設定されており、また算定された金額には端数処理が行われます。
これらのルールを事前に理解しておくことは、最終的に受け取れる補助金の額を正確に見積もり、資金計画を立てる上で非常に重要です。
予期せぬ金額の変動を避けるためにも、細かな規定まで確認しておく必要があります。
算出した補助交付額が補助対象経費を超える場合や、国などの他の補助金と合わせて経費を超える場合は、補助対象経費またはその差額が交付額の上限となります。
このため、複数の補助金を併用する際には、合計額が実際にシステム導入にかかる費用を上回らないように注意しなければなりません。
また、補助金額に千円未満の端数が発生した場合、その端数は切り捨てられます。
例えば、計算の結果99,500円と出た場合、実際に交付されるのは99,000円です。

補助金の計算で、千円未満は切り捨てられるのね。他の補助金も利用する際にどうなるか気になるわ

他の補助金と併用する際には、合計額が対象経費を超えないように注意が必要です
補助金は対象経費や他の補助金との兼ね合いで上限があり、計算された金額の千円未満の端数は切り捨てられます。
最終的な交付額を正しく把握するためにも、これらの規則を理解することが重要です。
補助金交付申請の要件と準備

福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業の補助金申請には、「誰が」「何に」「どのように」補助を受けるかの要件を正しく理解し、準備を徹底することが失敗しない申請の鍵です。
特に、工事着手前の申請や、福岡市税の滞納がないことなど、基本的な条件を見落とすと、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性があります。
みなさんも、補助金という言葉を聞くと、複雑で難しそうと感じるかもしれません。
しかし、一つ一つの条件を丁寧に確認すれば、確実に申請へと進めます。
補助金を確実に受け取るためには、申請者の資格、避けるべき行為、そして対象システムの技術的基準まで、細部にわたる確認が不可欠です。
まず「補助対象となる申請者の条件」として、どのような方が補助金を受けられるのかを明確に理解する必要があります。
次に、申請時に予期せぬトラブルを避けるために「申請における重要な禁止事項」を確認することは非常に重要です。
さらに、導入を検討しているシステムが補助の対象となるかを判断するため、「各補助対象システムの細かな基準」を深く理解してください。
最後に、「補助対象外となる具体的なケース」を把握し、ご自身の状況と照らし合わせることで、スムーズな申請準備を進めることができるでしょう。
これらの要件と準備事項をしっかりと把握し、計画的に進めることで、福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業の補助金を確実に受け取れます。
補助対象となる申請者の条件
福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業における補助対象者は、福岡市に居住し、市税の滞納がない個人や管理組合が対象です。
特に、補助金交付対象決定通知を受け取る前に、システムの設置工事に着手している場合や、システムが設置された住宅を購入しすでに入居している場合は、補助対象資格を失うという重要なルールがあります。
私が考えるに、この「工事着手前の申請」という点が、申請プロセスで最も見落とされがちなポイントの一つです。
| 補助対象者 | 戸建住宅へ設置する場合の条件 | 集合住宅へ設置する場合の条件 |
|---|---|---|
| 個人 | 自ら所有または居住する住宅にシステムを設置、またはシステム設置済み住宅を購入 | 自ら所有または居住する住宅にシステムを設置、またはシステム設置済み住宅を購入 |
| 管理組合 | 対象外 | 共有部分での使用を主な目的としてシステムを設置 |

私は集合住宅に住んでいますが、それでも補助金は利用できますか?

はい、集合住宅にお住まいの方や、管理組合も対象になります。
これらの要件をしっかりと満たしていることを確認し、補助金申請の第一歩を踏み出してください。
申請における重要な禁止事項
補助金申請プロセスの途中で補助対象資格を失わないためには、申請における重要な禁止事項について明確に把握しておく必要があります。
最も注意すべき禁止事項は、補助金交付対象決定通知が届く前に、システムの設置工事に着手することや、システム設置済み住宅にすでに居住していることです。
これは、事業の公平性を保ち、計画的な導入を促すための重要なルールとなります。
例えば、令和7年度の受付期間は令和7年5月7日から令和8年1月30日までと定められていますが、この期間内に「補助金がもらえるからすぐに工事を始めよう」と行動してしまうと、申請資格を失ってしまいます。
補助金交付対象決定前に工事を開始したり、設置済みの住宅を購入し入居したりした場合は、原則として補助金の対象にはなりません。

補助金申請から通知が届くまで、どれくらいの期間がかかりますか?

標準的な審査期間は20日ですが、書類の不不備があればさらに時間がかかる場合があります。
補助金を受け取るためには、これらの禁止事項を理解し、必ず交付決定通知後に工事を進める計画を立てることが不可欠です。
各補助対象システムの細かな基準
補助金を受けるためには、設置するシステムがそれぞれ定められた各補助対象システムの具体的な技術的要件や条件を満たしている必要があります。
例えば、リチウムイオン蓄電システムは「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が令和6年度以降に登録・公表する蓄電システムで、機器費が蓄電容量1kWhあたり13.5万円以下のシステム」と具体的に定められています。
V2Hシステムでは「電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を保有(または購入予定)していること」が必須条件です。
高効率給湯器(エコキュート)では、CO2を冷媒として使用する空気熱源ヒートポンプ給湯器であり、2025年度目標基準値以上の性能値を有するもの、またはおひさまエコキュートである必要があります。
| 補助対象システム | 主な要件 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 電力系統に接続し、発電電力を住居部分または共用部分で使用が目的、組み合わせ補助の場合はHEMS設置(既設も可)が必須 |
| リチウムイオン蓄電システム | SIIが令和6年度以降に登録・公表し、機器費が1kWhあたり13.5万円以下のシステム |
| V2Hシステム | 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が掲載している設備で、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を保有(または購入予定)していること |
| 高効率給湯器(エコキュート) | CO2冷媒空気熱源ヒートポンプ給湯器で、2025年度目標基準値以上の性能値を有するか、おひさまエコキュートであること |
| 家庭用燃料電池 | 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること |

すでに持っている太陽光発電システムを補助金と組み合わせることはできますか?

はい、既存の太陽光発電システムと組み合わせて他のシステムを導入する場合も、補助対象となります。
導入を検討しているシステムがこれらの具体的な基準をすべて満たしているか、事前に必ず確認することが重要です。
補助対象外となる具体的なケース
補助金制度を利用できない補助対象外となる具体的なケースを知ることは、無駄な手間を省き、適切な申請計画を立てる上で非常に重要です。
具体的には、賃貸住宅への設置や事業目的でのシステム設置は対象外です。
個人の場合、自らが所有または居住しない住宅への設置は補助対象となりません。
また、すべての補助対象システムは「未使用品」である必要があるため、中古品の導入は補助を受けられません。
さらに、算出した補助交付額が補助対象経費を超える場合や、国などの他の補助金と合わせて経費を超える場合は、補助対象経費またはその差額が交付額の上限となります。
そのため、国などの補助金を活用する場合、福岡市の補助金は減額される可能性があるため、全額が補助されるわけではない点も考慮が必要です。

中古の蓄電池システムは、やはり対象外なのですね。

はい、全ての補助対象システムは未使用品であることが必須です。
補助金制度を有効活用するためには、ご自身の計画がこれらの補助対象外のケースに該当しないか、綿密にチェックする作業が欠かせません。
申請から補助金受領までの流れ
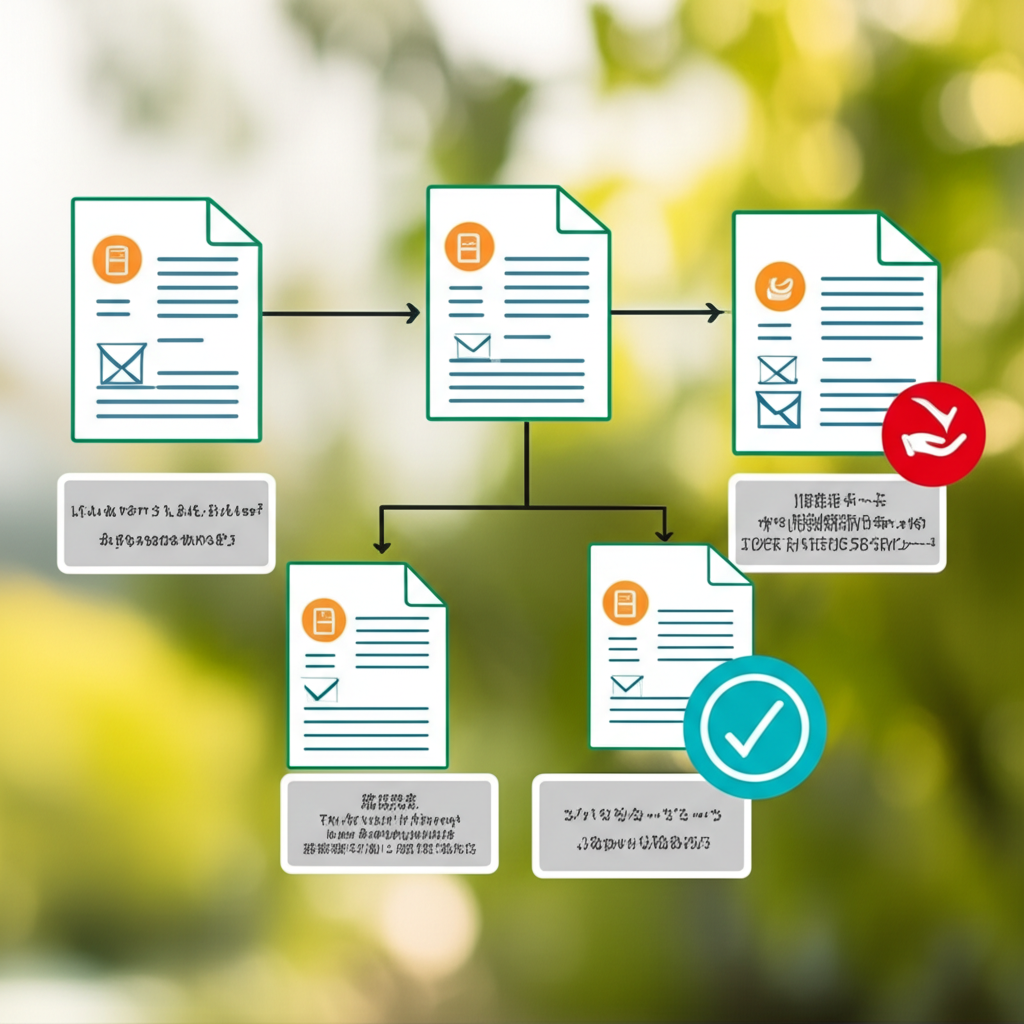
福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業の補助金を確実に受け取るには、申請手続きの各段階で正確な対応と期限厳守が不可欠です。
まず、工事着手前の「最初のステップ「交付申請」の手順」で必要な書類を提出し、次にシステム設置後の「設置完了後の「実績報告と請求」」を期限内に行い、最後に「補助金受領後の適切な管理義務」を果たすことで、スムーズな補助金受領へとつながります。
最初のステップ「交付申請」の手順
「交付申請」とは、補助金を受け取るためにシステム設置工事を始める前に行う最も重要な手続きです。
この申請を期限内に行わないと、補助金は一切受け取れません。
工事着手予定日、またはシステムが設置された住宅の入居予定日より前に、必要な書類を不備なく提出する必要があります。

いつまでに申請すればいいのか不安です。

余裕を持った計画的な提出が重要です。
申請書類の準備と提出は、計画的に行うことが成功への鍵となります。
設置完了後の「実績報告と請求」
システムの設置が完了したら、次に「実績報告と請求」の手続きを行い、実際に補助金を市に請求します。
この報告は、システム設置完了日または入居日のどちらか遅い日から60日以内、最終期限は令和8年2月27日(金曜日)までに、必要書類を提出することで完了です。

請求の期限を忘れてしまいそうです。

期限を過ぎると補助金がもらえなくなるので、早めの提出を心がけましょう。
設置完了後も気を抜かず、迅速かつ正確な書類提出が補助金受領のために必要です。
補助金受領後の適切な管理義務
補助金を受け取った後も、補助対象システムには管理義務が伴います。
たとえば、住宅用太陽光発電システムは17年間、リチウムイオン蓄電システムは6年間といった管理期間が定められており、この期間中にシステムを処分したり変更したりする際には、事前に福岡市の承認を得る必要があります。

補助金をもらった後も責任があるのですね。

承認なく処分や変更を行うと、補助金の返還を求められる可能性があります。
補助金を活用して導入したシステムを長く安心して使い続けるために、適切な管理と市のルール順守が求められます。
困った時の問い合わせ窓口情報
申請手続きで疑問や不明な点が出てきた場合、迷わず「福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局」に問い合わせることが、解決への近道です。
事務局は、平日9時から12時、13時から17時30分まで開いており、電話やメールで具体的な相談ができます。
住所は〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-20-35で、電話番号は092-517-9573、メールアドレスはfukuoka-jimukyoku@chugai-tec.co.jpです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事務局名称 | 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局 |
| 所在地 | 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-20-35 |
| 電話番号 | 092-517-9573 |
| メールアドレス | fukuoka-jimukyoku@chugai-tec.co.jp |
| 受付時間 | 平日 9:00~12:00、13:00~17:30 (土日祝・年末年始を除く) |

どこに連絡すればいいのか知りたいです。

公式の事務局が最も確実で正確な情報を提供しています。
些細な疑問でも、専門の窓口に相談することで、手続きのミスを防ぎ、安心して補助金を活用できます。
補助金申請成功のための最終確認
福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業の補助金を確実に受け取るためには、申請プロセス全体を通じた入念な最終確認が重要です。
まず、提出書類に不備がないか、すべての情報が正確に記入されているか、そして各手続きの提出期限を厳守できているかを改めて確認することが求められます。

申請前に確認すべきポイントを教えてほしいです。

すべての要件を満たしているか、ダブルチェックで確認することが成功の鍵です。
最終確認を徹底することで、不備による再提出や申請却下のリスクを最小限に抑え、スムーズな補助金受領へとつながります。
全体の流れを理解し、準備を怠らないことが、補助金活用の成功を決めます。
よくある質問(FAQ)
- 福岡市の補助金と国や他の自治体の補助金は併用できますか?
-
はい、福岡市の補助金は国や他の地方自治体の補助金と併用できます。
併用により、導入費用を最大100万円以上お得にできます。
ただし、複数の補助金合計額が対象経費を超えないよう、注意が必要です。
- 太陽光発電システムの工事を始めてから補助金を申請できますか?
-
いいえ、システムの設置工事に着手する前に補助金の申請が必要です。
補助金交付対象決定通知を受け取る前に工事を開始すると、補助対象資格を失います。
- 中古の太陽光発電システムや蓄電池は、福岡市の補助金の対象になりますか?
-
いいえ、補助対象となる全てのシステムは未使用品である必要があります。
中古品の設置は補助対象外です。
- 賃貸住宅に住んでいますが、福岡市の補助金を利用して太陽光発電システムを設置できますか?
-
いいえ、個人の場合、賃貸住宅への設置や事業目的でのシステム設置は補助対象外です。
自らが所有または居住する住宅への設置が条件となります。
- 住宅用太陽光発電システムを導入する場合、HEMS(家庭向けエネルギー管理システム)の設置は必須ですか?
-
住宅用太陽光発電システムを「組み合わせ補助」で導入する場合、HEMSの設置は必須です。
すでにHEMSを設置している場合もこの条件を満たします。
- 補助金はいつ頃申請するのが良いですか?
-
補助金の予算には限りがあり、予算がなくなり次第受付が終了します。
年度の初め頃に申請が集中する傾向があるため、早めの情報収集と計画的な準備が重要です。
まとめ
福岡市が提供する住宅用エネルギーシステム導入支援事業は、高額な初期費用がネックになりがちな太陽光発電や蓄電池などの導入を強力に後押しします。
特に、国や他の地方自治体の補助金と併用することで、最大100万円以上お得になる可能性があり、家計と地球環境の両方に貢献できるまたとない機会です。
- 申請は工事着手前に行うこと
- 予算には限りがあり、早めの申請準備が重要であること
- 戸建・集合住宅ともに太陽光発電や蓄電池、V2Hシステムなどが補助対象であること
- 専門の事務局が問い合わせ窓口になること
この貴重なチャンスを逃さず、ぜひ積極的に制度を活用し、未来に向けた賢いエネルギー選択を実現してください。
よくある質問(FAQ)
- 福岡市の補助金と国や他の自治体の補助金は併用できますか?
-
はい、福岡市の補助金は国や他の地方自治体の補助金と併用できます。
併用により、導入費用を最大100万円以上お得にできる可能性もございます。
ただし、複数の補助金合計額が対象経費を超過しないよう、注意が必要です。
- 太陽光発電システムの工事を始めてから補助金を申請できますか?
-
いいえ、システムの設置工事に着手する前に補助金の申請が必要です。
補助金交付対象決定通知を受け取る前に工事を開始すると、補助対象資格を失いますので、十分ご注意ください。
- 中古の太陽光発電システムや蓄電池は、福岡市の補助金の対象になりますか?
-
いいえ、補助対象となる全てのシステムは未使用品である必要があります。
中古品の設置は補助対象外となります。
- 賃貸住宅に住んでいますが、福岡市の補助金を利用して太陽光発電システムを設置できますか?
-
いいえ、個人の場合、賃貸住宅への設置や事業目的でのシステム設置は補助対象外です。
自らが所有または居住する住宅への設置が条件です。
- 住宅用太陽光発電システムを導入する場合、HEMS(家庭向けエネルギー管理システム)の設置は必須ですか?
-
住宅用太陽光発電システムを「組み合わせ補助」で導入する場合、HEMS(家庭向けエネルギー管理システム)の設置は必須要件です。
すでにHEMSを設置している場合も、この条件を満たします。
- 補助金はいつ頃申請するのが良いですか?
-
補助金の予算には限りがあり、予算がなくなり次第受付が終了します。
年度の初め頃に申請が集中する傾向があるため、早めの情報収集と計画的な準備が重要です。
